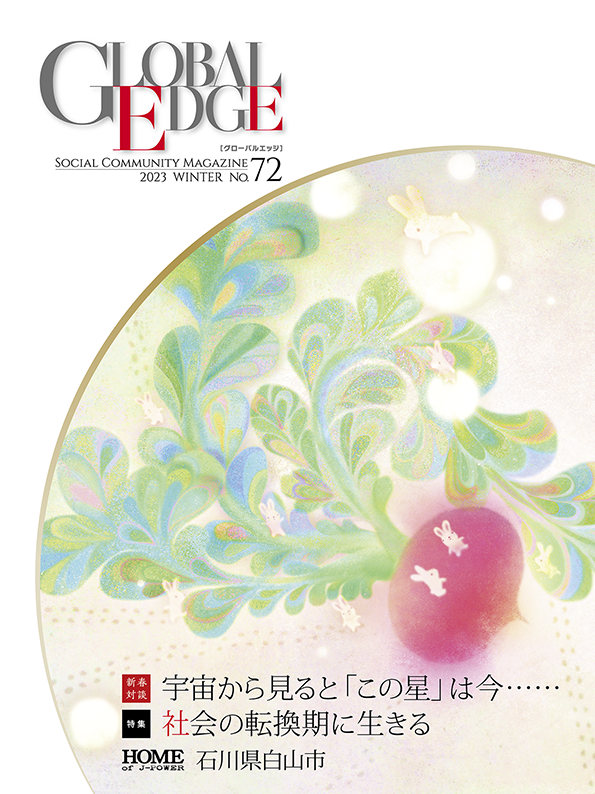霊峰白山の恵み 水の力を感じる
藤岡 陽子
Home of J-POWER
石川県白山市と手取川第一発電所を訪ねて

日本三名山のひとつで、神が宿ると称される白山。J-POWER手取川第一発電所は、白山を水源とする手取川を利用して発電している。山の恵みと、水の力を感じようと、石川県白山市を旅して歩いた。
作家 藤岡陽子/ 写真家 大橋 愛
獅子吼高原の頂きから手取川扇状地を一望
晴れ渡った秋の日に、ゴンドラに乗って獅子吼(ししく)高原の山頂を目指した。
標高約650mの頂きから手取川扇状地を一望し、川の流れを目で追っていく。
流れは山間から平地、そして日本海へ──。
昔は暴れ川と怖れられ、何度も氾濫を起こした手取川。
だがいまはゆるやかに、穏やかに、流域の田畑に豊かな水の恵みを与えながら曲線は続いていく。
すぐ目の前で、色鮮やかなパラグライダーが羽根を広げた鳥のように舞い上がり、私の心をも大空へと連れていってくれる。
明るく軽やかな旅の始まりに胸が震えた。




水に対する感謝と畏怖 禊を通して自然を思う



霊峰白山と、山がもたらす水の恵みを学ぶため、三宮町にある白山比咩(しらやまひめ)神社を訪れた。
老杉がまっすぐに天を衝く姿に圧倒されつつ表参道を抜けた先、出迎えてくださったのは田中天善(たかよし)権禰宜(ごんねぎ)。田中さんに神社と水との関わりについて教えていただく。
「私たちの変わらない信仰は、白山からいただく水の恵みに感謝を捧げることです。また恵みだけではなく、水の災いがないようにと祈っております。水に対する感謝と畏怖の念をもって、手を合わせているのです」
白山比咩神社は全国に3,000余りある白山神社の総本宮で、菊理媛命(くくりひめのみこと)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)がご祭神として祀られている。
このご祭神であられる菊理媛命が、伊弉諾尊に禊(みそぎ)を促したとされる記述が「日本書紀」にあり、こうしたいわれからも神社では古くから水を崇めてきた。
田中さんたち神職は1年を通して禊修行を行い、4月から11月までの月に2回は一般の人からも参加を募る。
「禊をすることで水を身近に感じていただきたいという思いとともに、自然に親しむ機会になればと考えています。春先は水が冷たく、冬は温かく感じます。草木の色づきやアメンボ、トンボなど季節の虫にも目を向け、自然と共生する体験をしていただければ」
水は生命をつくり出すもので、目に見えないけがれを清める力を持っている、と話す田中さん。
紀元前91年に創建されてから約2,100年間、白山比咩神社は水への感謝を神に捧げ、人々に伝え続ける存在であると知る。









七ヶ用水の機能と歴史 世界かんがい施設遺産に登録
白山を源流とする手取川は石川県最大の一級河川で、流れが弱まる山間から平地に注ぐ先で扇状地をつくってきたという。
一般的に、扇状地は水はけがよすぎて稲作には向かないとされている。そのため手取川扇状地では鎌倉時代から用水が引かれ、米や他の農作物を育てる努力を続けてきた。
扇状地に張り巡らされた用水のことを詳しく知りたいと思い、手取川七ヶ(しちか)用水土地改良区白山管理センターに向かう。
白山管理センターは白山町にあり、こちらに30年以上勤めておられる中川晃さんにお話を聞かせていただいた。
「現在の七ヶ用水は、白山市、金沢市、野々市(ののいち)市、川北町の農地に水を運んでいます。水路の全長は約140km、面積でいうと4,500haに及びます。水田に農業用水を供給する水路なので、農業の組合員の方々からの会費で、運営しています」
手取川は「七たび流れを変えた」と伝承されるほど氾濫の多い川で、ダムができるまでは、用水をつくってもすぐに壊されることの繰り返しだったという。
「白山管理センターは、この地で水と向き合ってきた歴史を伝える役割もあるんです」と中川さんが言うように、施設には手取川と格闘してきた人々の軌跡が、写真や文章で展示されていた。
「2022年8月4日にも大雨が降って、手取川が越水したんです。川の水位があれほど増すのを目にしたのは初めてでした」
明治時代につくられた大水門の位置まで水位があがり、石や木が流れこんできた。流木が当たって壊れたスポットライトはいまもそのままになっている、と中川さんが眉をひそめる。
そうした水害が起こった際には水利施設総合管理システムで遠隔操作を行って防災に努めているそうで、「今回も大きな被害はなかった」と危機を振り返った。
2014年には「世界かんがい施設遺産」に登録されたという七ヶ用水。これからも現役の施設として水の恵みと脅威、その両側面を多くの人に伝えていただきたいと切に願う。






100年先もこの地で持続可能な酒づくりを
安吉町(やすよしまち)に蔵を構える吉田酒造店では7代目の社長、吉田泰之さんが時代を見据えた新しい酒づくりを実践していた。
「日本酒はとても繊細で、温度管理が重要です。ですがそのために多大な電力を使っているのも事実。そこで私は、10℃前後で保管できる日本酒をつくれないかと試みているんです」
たとえばマイナス5℃で保管する日本酒をつくると、移送中も販売先でもその温度をキープしなくてはならず多大な電力を消費する。
日本酒づくりは大量の電力を消費するものだ、という現代の常識を変えていきたいと吉田さんは考える。
「冷蔵庫で冷やす理由は、日本酒の酸化を止めるためです。日本酒には酸化防止剤が入っていないので、しかたがないことなんです。でも私は、冷やす以外に日本酒が酸化しない方法がないかと研究しているんですよ」
空気に触れると酸化が進むので、発酵させてからすぐに搾って瓶詰めする。それだと10〜15℃でも品質は維持できるはずだと吉田さんは話す。そのために搾った真横で瓶詰め作業ができるよう、作業場の配置を変えてみたという。
創業150周年の2020年に7代目社長に就任した吉田さんは新銘柄「吉田蔵u」を立ち上げ、1本売り上げるごとに10円、環境保全活動に寄付を始めた。
電気を使わず自然の状態のまま発酵させ、美味い酒ができるかどうか、手取川ダムの監査廊と鉄管搬入路横坑(よここう)の2カ所を使って熟成させる実験も行っている。
「日本酒は自然のおかげで成り立っています。だから品質を重視しながらも自然を損なわない、5年先、10年先の未来に繫がる酒づくりを目指したいと考えています」
と口にする吉田さんに迷いはなく、自然に対するまっすぐな思いが眩しかった。
100年先に生きる人が、きちんと幸せでありますように──。
水と対話をしながら歩いた道は、私たちがいまなにをすべきかを教えてくれたように思う。
気温約10℃の監査廊で日本酒の自然熟成を試みる

堤体に立ってダムを見下ろせば、鉱物の硬さを感じさせない滑らかなカーブが下方まで続いている。
冬のはじまりに訪れた手取川ダムは、山の紅葉を湖面に映し、眩しいほどに美しかった。
「手取川ダムは岩石や土砂を積み上げて造ったロックフィルダムです。高さは153mありまして、同型式のダムの中では日本で4番目の高さになります」
案内してくださった田中学所長によると、手取川発電所の発電出力は25万kWで、北陸地方最大規模であるという。大規模水力発電所として1979年に運転を開始して以来、手取川ダムは治水や都市用水など多方面で利用されているのだと教えていただく。
「実はいま、発電所で新しい試みをしているんですよ」
その試みとは地元の吉田酒造店と協力し、1年を通して10℃前後の温度を保つダムの監査廊と鉄管搬入路横坑で日本酒を熟成させるというものだ。
実験的に保存されている日本酒を見せていただくため、長い階段を下り、監査廊内へと入っていく。
田中所長の後をついて歩くこと十数分……。ついに通路の端に置かれたコンテナを発見!
段ボールの箱の中には「手取川」と、新銘柄「吉田蔵u」シリーズの「石川門」、「百万石乃白(ひゃくまんごくのしろ)」が大切に保存されていた。
「美味しいお酒ができるのが今から楽しみです。こうして白山の魅力を発信していきたいですね」
と日本酒が入った瓶を指差し、田中所長が嬉しそうに微笑む。
ダムと日本酒。その意表を衝くコラボレーションは、きっと新たな観光資源になるに違いない。
「手取川ダム、カンパーイ!」
とグラスを合わせる日を楽しみにしています。











手取川第一発電所
発電出力:250,000kW
運転開始:1979年8月
所在地:石川県白山市東二口
Focus on SCENE 総本社へ続く静粛な参道
白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)の表参道は、樹齢800年を超える杉の木などの樹木の間を抜ける約250mの参道。一の鳥居からのなだらかな階段は108段あり、二の鳥居、三の鳥居を過ぎて本殿に行き着く。白山比咩神社は、全国に約3,000社あると言われる白山神社の総本社で、白山(はくさん)をご神体とし、古来、恵みの水の神として崇められてきた。暴れ川として知られた手取川が形成した白山市の扇状地の要の位置にあるのは手取川に静まってほしいと願う人々の思いがあったからだろう。地元の人からは親しみを込め、「しらやまさん」と呼ばれている。
文/豊岡 昭彦

写真 / 大橋 愛

PROFILE
藤岡 陽子 ふじおか ようこ
報知新聞社にスポーツ記者として勤務した後、タンザニアに留学。帰国後、看護師資格を取得。2009年、『いつまでも白い羽根』で作家に。最新刊は『空にピース(2022年、幻冬舎)』。その他の著書に『満天のゴール』、『おしょりん』など。京都在住。