“こつこつ”と積み上げるブランドの真価
渡部 肇史×高野 登
新春対談
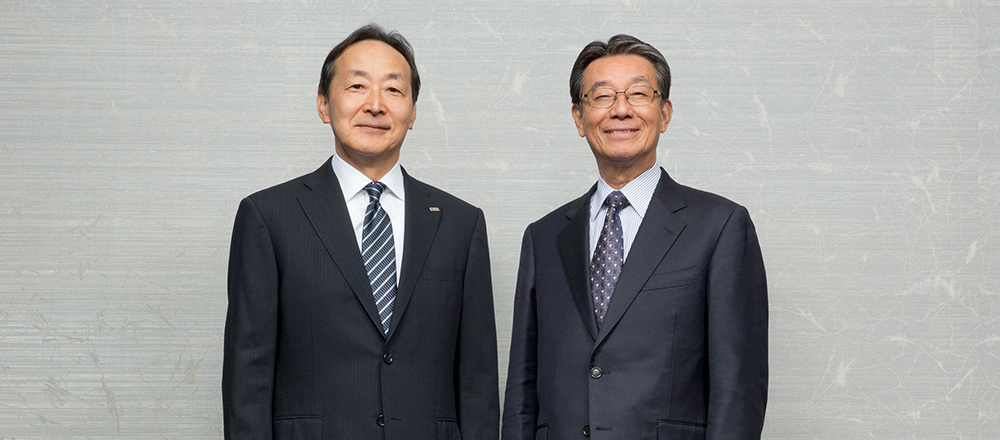
J-POWER社長
渡部 肇史
人とホスピタリティ研究所所長
高野 登
「至高のホスピタリティー」を掲げて世界のホテル界にその名をはせるザ・リッツ・カールトン。かつて日本支社長を務め、現在は人間関係に伴うコミュニケーションをテーマとしたセミナーなどを行っている高野登さん。
高野さんが語る、揺るぎないブランド価値を生み出す方法は地道で人間味あふれるものだった。
教えられるサービスと創意工夫するサービス
渡部 国内外の一流ホテルに長く身を置き、接客業を極められた高野さんが、少年期まではむしろ人見知りだったと伺いました。
高野 人と会うのが苦手で、家に誰か来ると押し入れに隠れるような子どもでした。薄暗い中、空を飛べたら何が見えるか、海の底には何がいるかと想像を膨らませて考えるのが好きだったんです。
渡部 そのようなご性格は、ホテルで働く上で役に立ちましたか。
高野 接客サービスには人に教えられるものと、自分で創意工夫するものがあります。学校や職場で仕込まれて一通りをできるようになったら、自らの想像力を駆使して仮説を立ててやってみる次の段階が求められます。私は想像力を働かせることが得意だったので、ホテルでの修業時代から仕事のやり方が自分の性に合ったのか、ストレスなく仕事ができました。
渡部 ヒルトン、ウェスティン、プラザなど、それ以前に働かれたホテルも一流どころばかりですが、ザ・リッツ・カールトンはどこが決定的に違ったのですか。
高野 私は、自分なりの工夫でお客様に一段上のサービスを提供したいし、現にやってきたと自負していたのですが、リッツ・カールトン創業者のホルスト・シュルツィさんから「サービスは一面で科学である。が、その科学を超えたところにホスピタリティーの世界がある」と教わりました。私の考えるサービスはまだ場当たり的で、体系づけなければならないと気づかされたのです。
渡部 そもそも、リッツ・カールトンの代名詞である「至高のホスピタリティー」を、日々の仕事に落とし込んでいくのは容易ではないですよね。
高野 簡単ではありませんが、毎日企画を立てる機会があることで、鍛えられました。リッツ・カールトンでは「人生そのものが企画の連続」と捉え、スタッフ個々がそれぞれの持ち場で発案した企画に対して、人をわくわくさせるか、新しい価値を生み出すか、人を幸せにするかという3つの観点から検討を加え、日々実践に移していくのです。
渡部 現場を知るスタッフ一人ひとりの創意工夫を集めて、大きなくくりの中でホスピタリティーを高めていく。その積み重ねが大事なのですね。
高野 皮肉なもので、正しく提供されたサービスはお客様の印象に残らず、よくなかったサービスが記憶に残ります。ですから、お客様の胸に刻み込まれる正しいサービスとは何かと、必死になって企画を立て続けることが評価につながるのです。
持ち味をすくい上げ 得意分野を伸ばす仕組み
渡部 常に世界のトップに列せられるリッツ・カールトンが、その評価をずっと維持する難しさは余人の想像を超えると思います。むろん大本の経営理念や、それを実践に移すための戦略・戦術があってのことでしょうが、現に働いておられるホテルマンの姿にも、そうした芯になるものが浸透し、しっかり共有されていることを感じます。
高野 私の現役時代を振り返っても、リッツ・カールトンで働く喜びや誇りは、ちょっとほかでは味わえないものでした。その芯にあるのが「クレド(信条)」で、中でも基本的な信念(ザ・リッツ・カールトン・ベーシック)は有名です。すべての社員は常日頃、小さなクレドカードを携帯して仕事に当たっています。クレドはリッツ・カールトンの哲学であり、それを胸に抱いた一人ひとりがある種のオーラを発して、お客様にも伝わるのかもしれません。
渡部 月並みな愛社精神を超えていると感じます。他を寄せつけないホテルで自分は働いているという充実感や自負心を、きっとみなさんが抱いていて、企業のあり方として1つの理想形ではないでしょうか。もちろんJ-POWERにも明確な企業理念があり、全社員がそれに適った働き方をしてくれていますが、社員一人ひとりにより深く浸透し、社外へも伝わっていく点は、ぜひ範としたいと思います。
高野 クレド経営は業界を超えて知られるようになり、また、多くのホテルマンがリッツ・カールトンで働きたいとやって来ます。ただ実際に入社すると、こんなにも大変な職場かと愕然とする。なぜなら、その人の可能性を引き出すことを日々求められ続けるからです。自分の可能性を決して見くびってはならない、あなたの得意分野を突き詰めろと背中を押され続けます。
渡部 一人ひとりの持ち味をすくい上げ、得意な分野を伸ばしていく仕組みが全社的に組み込まれているのですね。それは相当なプレッシャーでしょうね。
高野 ええ。でも求め続けられることに耐えて、自分でも気づかなかった可能性を引き出された社員は、日々の実践を通じて、「こんなにすごい仕事ができるのか!」と目覚めますから、あとはギューンと伸びていくだけです。
スタッフに権限を譲り「動く」を後押しする
渡部 他に類例を見ないという点で、エンパワーメント(権限委譲)にまつわる制度も独創的です。リッツ・カールトンの社員には1日2,000ドルまでの決裁権があると聞いて、ちょっと耳を疑ったのですが……。
高野 社員一人ひとりが自分で判断し、行動する力が与えられており、接客の場で起きた問題に金銭を伴う解決策が求められても、個人の判断で決裁してよいのです。願望やニーズはそれが最高潮の時に満たされることで感動を生みます。お客様のニーズや要望になんとしても応えたいという気持ちやアイデアが冷めてしぼんでしまう前に、行動に移すための後押しをするわけですね。
渡部 クレドの信念や価値観が身についたホテルマンなら、とっさの判断を誤ることもないのでしょう。2,000ドルという金額に根拠はあるのですか。
高野 かつて米国のリッツ・カールトンで実際にあった話です。大切なお客様がホテルに置き忘れた荷物をボストンからサンフランシスコまで送り届けた際、スタッフが用いた往復航空券の代金がその額でした。急を要する荷物で、お客様が取りに戻ったり、別の輸送手段に委ねたりでは間に合わないと知り、自分で届けるよりないという現場の判断が尊重されたのです。
渡部 似たようなケースは国内でも起きることがあるのですか。
高野 大阪から東京に荷物を届けた例があります。それに要する金額の多寡はともかく、この制度の本質が「人も組織も動かすものではなく、動くものである」というリッツ・カールトンの考え方にある点が重要なのです。信念に裏打ちされた「動く」を優先する。自分が信頼されて仕事を任され、存在価値を認められて、居場所があると実感できる時、人は動かされる前に動きたくなる。そうした環境のもと、あなたの判断で、感性で動いていいと言われたら、誰だって動き出さずにはいられません。
渡部 確かにそうですね。人間教育の核心をお聞きしているようです。
高野 そういう刹那に、とりあえず上司の判断を仰ぐとか、経理のハンコをもらうとか手間取っていれば致命的にタイミングを失する恐れがあるし、せっかくの「動く」エネルギーが無に帰してしまいかねません。つまり、動こうとする人の主体性を消さないための権限委譲なのです。
渡部 よかれと判断して動いた結果が裏目に出たら、その人の処遇はどうなるのですか。
高野 失敗したっていいんです。いろいろ失敗をくぐり抜ける中で、自分の感性を磨くことこそが重要です。ただプロである以上、同じ失敗を繰り返せば笑われるという話です。
全員野球の一糸乱れぬ連携プレーを目標に
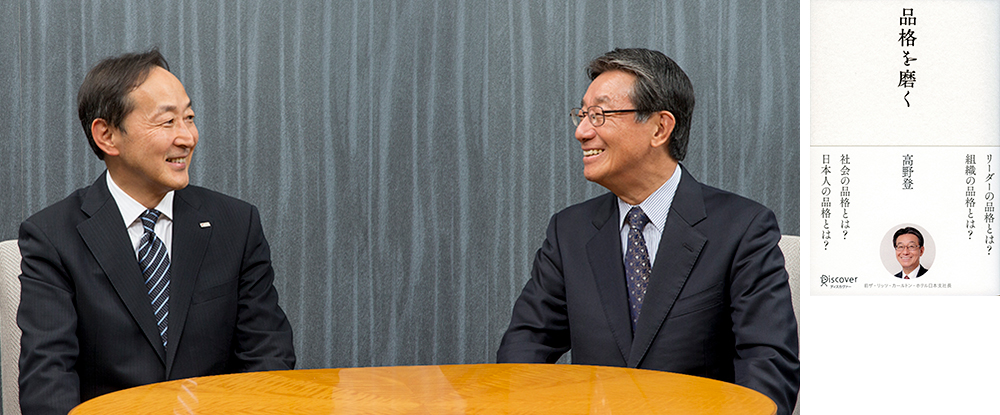
渡部 ホテル業にあっては、いろいろな職種・職能を帯びたスタッフが同時並行的に働いて、極論すれば全員で1人のお客様をもてなす局面もあると思います。我々にも似たところがあって、各職域に高い技能を持った人や専門性に長けた人がいて、彼ら全員が働く目的や使命を共有し、力を合わせることで初めて電気がつくられるし、安定供給が可能にもなるわけです。
高野 まったく同じだろうと思います。私が企業の人財についてよく言うのは、いきなりホームランバッターを育てようとせずに、まずはバントでこつこつかせぐ選手を育てなさいと。全員野球という言い方が示すように、誰かが突出して目立つチームよりも、メンバーは小粒でも意思統一が図られているチームのほうが結局は強いのだと、私は確信しています。
渡部 社内を見ていて、円滑なチームプレーができていると仕事がチェーンのようにつながっていく実感があります。製造業などで「後工程に迷惑をかけない」という言い方がありますが、全員が自分の後を引き受ける人を思いやって動けば、ライン全体が継ぎ目なくつながり、各自が仕事の流れを把握しやすくもなります。
高野 その意味で、全員野球の一糸乱れぬ連携プレーを第一義とすべきなのですが、ただ、いつまでもバントのチームでは予想以上の結果は望めません。みんながヒットを打てる、ここ一番では長打も出るような底上げが必要で、それにはチーム内にスタープレーヤーが欲しい。その人の目線の高さを通じて、他の人の可能性まで引き出されることが狙いで、たまにホームランをかっ飛ばしてくれたらサービスにも彩りを添えられます。
渡部 私もそれに近いことを前々から感じていて、チーム内の他のメンバーから「あの人のようになりたい」と目標にされる人間がいるとチーム全体によい影響が出て、動きもよくなります。社内外に向けて存在感をアピールしつつ、組織を活性化するためにスタープレーヤーを養成せよという今のご指摘に、わが意を強くしました。
マニュアルやデータを超えて働く「感性」とは
渡部 感性を磨く、感性を働かすことが大切とのお話でしたが、実は我々にも「感性」は欠かせない素養の1つなのです。日頃、発電所などでハードウエアを相手に、スペックやマニュアルがかっちりした中で働いていますが、最後のところでは「五感を働かせよ」と技術担当の副社長がよく言っています。
高野 それは、例えばどういった場面ですか。
渡部 運転中の発電設備からは様々な機械音が出ます。そのような環境下ではわずかな音の変化を聞き分けて、異常が発生していないかを感じ取る力がとても重要です。石炭火力発電であればボイラー内の炎や熱せられた部分の色・温度の変化などが要チェックですし、もしも異様な臭いを感じたら即座の対応が必要だとか、マニュアルやデータを超えたところで人間の五感がものをいう局面が多々あります。
高野 目や耳や鼻で感じるにとどまらず、その背後で何が起きているかを察知し、適切な対応を取ることまで含めた感性であるなら、ホテルマンもまったく同じです。マニュアル通りの接客で事足りると思うのと、お客様が何にお困りで、何をお求めかを察知して即座に、時には先回りして動くのとでは、見かけのサービスは同じでも、お客様への伝わり方がまるで違ってきます。とどのつまり、自分が働くのは誰かの幸せや豊かさのためだと気づくことに、感性を磨く意味があるのではないでしょうか。
渡部 我々で言えば、与えられた業務を淡々とこなすのと、自分たちのつくる電気がエンドユーザーに届いて、家族の団欒や街の賑わいを明るく照らすシーンを思い描いて働くのとでは、身につく感性にだいぶ開きが出るかもしれません。
高野 結局、働き方の問題に行きつくと思うのです。創業者シュルツィさんの言葉に「あなたという存在の何が周りの人を幸せにしているか?」というものもあり、ここで働く限りは自らに向けてそう問い続けることが求められます。だからリッツ・カールトンで働く人はメイドもドアマンもウエイターも、お客様の幸せを日々考え続けることが習い性になってしまう。これこそが、リッツ・カールトンでの働き方なのです。
渡部 シュルツィさんはホテル業界に数多くの金言をもたらした方で、旧来の「ホテルマンは召使たるべし」といった概念も変えたそうですね。
高野 リッツ・カールトンのモットーである『We Are Ladies and Gentlemen Serving Ladies and Gentlemen(紳士淑女たるお客様にお仕えする、私たちもまた紳士淑女である)』は、彼がホテル学校時代に書いた論文のタイトルです。お客様とホテルマンを同格と見なすとは何事かと、当初は理解を得られなかったようですが、いまやリッツ・カールトンのホスピタリティーを簡潔明瞭に言いきった金看板になっています。

「こつこつ」積み上げる揺るぎない価値と力
渡部 ここまで、リッツ・カールトンという確固たるブランドを支えているバックグラウンドをご紹介頂きました。
わが身に置き換えてみて、昨今、規制緩和による業界内の競争環境の中で、自社のブランド力というものを意識せざるを得なくなっています。ブランドを確立するに当たり、高野さんはどのようなことが大切になるとお考えですか。
高野 私は電力業界に詳しいわけではありませんが、一般論として、企業の経営判断として優先すべきはスピードかプロセスかという問題が常にあります。要するに効率優先か、愚直に進むかの二者択一なのですが、私の見たところ前者をとった会社は軒並み勢いをなくし、後者を選んだ会社が成果を上げ、ブランドを確立しています。では、リッツ・カールトンはといえば明らかにプロセス重視で、愚直に結果を積み上げてきた先に、今日の姿があります。
渡部 我々も創業以来ずっと愚直に歩んできた半面で、近年速まる一方の世の中の動きに応じて効率にも重きを置かねばなりません。我々にとりましてもいかにしてプロセスとスピードのベストバランスを見つけるかが、非常に重要なテーマになっています。
高野 であるならば、そのテーマを全社で共有し、各部署・各チームに降ろして、一人ひとりが企画マンになってアイデアや意見を出し合う形で、活況に導く方法もあるのではないでしょうか。スピードは遅くてもいいから、プロセスの中で人財を、会社を育てていこうと愚直に進んだ先に、未来も拓ける。リッツ・カールトンは決して「急がない」会社で、企業体質を一言で表現するなら「こつこつ」なんです。
渡部 我々の「こつこつ」を1つ言いますと、競争社会を勝ち抜くという観点よりも、自分たちの使命や目的はこうだという理念が先に立ちます。必要以上に勝ち負けにこだわらない美風のようなものがあります。
高野 リッツ・カールトンも無闇に競争はしません。いかにして戦わずに済む舞台をつくろうかと、戦いを省略するための「戦略」を立て、考えに考え抜いて積み上げてきたあれこれが、言うなればブランド力となったのでしょう。
渡部 こつこつ積み上げたからこその、揺るぎない価値と力……我々もそれに倣って、電力ビジネスならJ-POWERに話してみよう、J-POWERなら信頼できる、J-POWERとまた仕事がしたいと、広くみなさんに知られ、評価していただける会社になりたいと思います。
今日は本当にありがとうございました。
高野 こちらこそありがとうございました。
構成・文/内田 孝 写真/大橋 愛


PROFILE
高野 登(たかの・のぼる)
人とホスピタリティ研究所所長、元ザ・リッツ・カールトン日本支社長。1953年、長野県生まれ。プリンスホテルスクール(現・日本ホテルスクール)第1期卒業後に渡米。ニューヨーク・プラザホテル、ロサンゼルス・ボナベンチャーホテル、 サンフランシスコ・フェアモントホテルなどでの勤務を経て、90年ザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わる。94年ザ・リッツ・カールトン日本支社長に就任後、大阪、東京の開業をサポートし、2009年同社を退職。10年に人とホスピタリティ研究所を立ち上げ、全国各地で人材、組織、地域づくりのコンサルティングに当たっている。


