自然と共生する暮らしへ
建築で境界をなくすことの意味とは
村山 均×隈 研吾
Global Vision
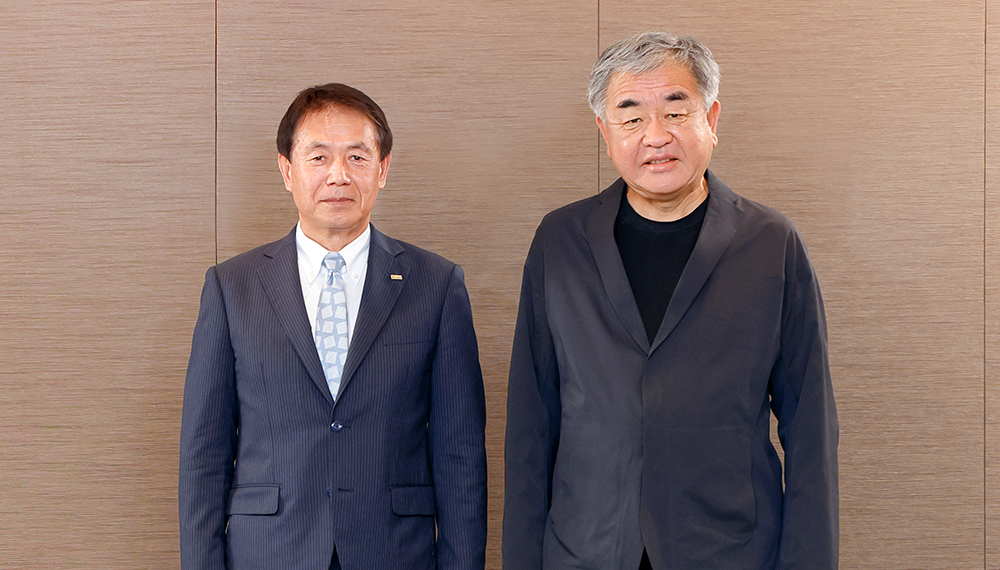
J-POWER会長
村山 均
建築家、東京大学特別教授・名誉教授
隈 研吾
30以上の国や地域でプロジェクトが進行中という建築界の巨匠。
「地方と自然」、「小さなシステム」、「負ける建築」といったキーワードで世界をつくり替えようと東奔西走する、「境界を持たぬ人」である。
地方にこそある日本の宝 その場所に密着した建築を
村山 先日、私は出張先のオーストラリアで、隈さんの建築作品を拝見する機会がありました。シドニーの人気スポット、ダーリング・ハーバーの中心に立つ「The Exchange」という大変に個性的かつ魅力的な建物でした。
隈 あれは高層ビルに囲まれた広場の中心に、周りの角張った景観とは対照的にランダムな円筒形の建物を置き、その周囲を木製のファサードをぐるぐる巻きにした「鳥の巣」のような形をしています。地上階にレストランやマーケット、上層階には図書館と幼稚園があって、建物全体で「まちと人をつなぐ複合施設」の役目を担っています。
村山 建築デザイン上のハイライトは、誰もがホッと息をつけそうなあの外観にあると思います。見た目には、絹糸を幾重にも巻きつけた繭玉のようでもあり……。
隈 あるいは、海辺という場所柄から貝殻をイメージする人もいるようです。公園広場とうまくなじむ形で木の素材感を活かそうと、高耐久化天然木材のアコヤをしなやかな形に曲げ、細長くつなぎ、曲面ガラスをはめこんだ壁面の外側に巻きつけてあります。一見、非常に複雑怪奇な構造のようでいて、つくり方としては至極シンプルで、コストも抑えられる工法なのです。
村山 あの作品に限らず、隈さんは日本の伝統建築を再評価し、特に素材としての木に注目して、数々の建築作品へ自在に取り入れておられます。そしてそこには、建築に向き合う姿勢として「内と外の境界を曖昧にし、自然と共生する暮らしへ」という信念があるそうですが、そのような境地にどうやってたどり着かれたのでしょうか。
隈 ターニングポイントは1991年に起きたバブル経済の崩壊でした。その5年前に最初の設計事務所を開いた当時はバブル真っ盛りで、都市部に大きな建物を次から次へとつくり続けました。ところがバブルが弾けた途端、東京での案件が軒並みキャンセルになった時に、地方を回って仕事を探し始めたわけです。
村山 バブル崩壊が地方に着目するきっかけになったのですね。
隈 すると、自分の想像をはるかに超えて、日本の地方には多様性と優れた特徴があると分かってきました。腕利きの職人も大勢いるし、材料にしても木や和紙などの素晴らしい素材がふんだんにある。実は、日本の宝は地方にこそあるのではないか……ならば、自分のつくり方を一から考え直すしかないと腹を括りました。
村山 都市から地方へ視線を移せば、建築も従来とはまったく違うものができそうです。
隈 ローカルな自然資源やクラフトマンシップと一体になって、その場所に密着した建築をつくっていきたい。そうすることがその地域の人たちを幸せにするし、日本の可能性を拓くという気づきが、私にとって一番の転換点になりました。


自然に包まれ、地域とつながる北海道東川町のオフィス空間
村山 そういう視線の延長線上なのか、隈さんは昨年5月、北海道の東川町に斬新なデザインのオフィス空間をつくられました。これは東川町と隈研吾建築都市設計事務所とのコラボ企画とのことですが、どのようなプロジェクトなのですか。
隈 旭川市に隣接し、人口1万にも満たない東川町は近年、移住者が増え続けていることで有名です。木工家具の産地である地域性を活かしつつ、ワーク・ライフ・バランスのモデル空間となる提案にあふれたサテライトオフィス「KAGUの家」をこの地に築き、地域産業の活性化や新しい産業の創出を目指そうと精魂を傾けています。
村山 東川町は国道や鉄道などの交通の便に恵まれず、上水道も整っていないとか。常識に照らせば住みやすいとは思えませんが、なぜ多くの人が、特に若い世代が引き寄せられるのか……何か特別なポテンシャルが備わっているのでしょうか。
隈 まずは大自然の美しさや豊かさに圧倒されて、水道がないのも天然の湧水で生活を賄えるからだと納得がいきます。恵まれた自然環境だけならほかにもありますが、ここにはヒューマンスケールの「まち」が共存していると気づいて、生活の場にしたくなるのだと思います。米国では、1マイル以内の生活圏で必需品や魅力的なものが手に入ることが住みやすさの目安とされますが、まさに東川町は「1マイル生活圏」の条件を満たしているのです。
村山 ヒューマンスケールと大自然が共存する場となると容易には見つからないわけですね。それで若い人たちが地域に根づいて暮らし、働くためのサテライトオフィスをつくられたと。その4棟ある「KAGUの家」の1つには、ご自身の設計事務所も入居済みと伺いましたが。
隈 はい。日頃、我々の仕事場は都会にあって、物理的にビルの中で働いていると人間関係もビル内で完結し、外部との交流はまずありません。コロナ禍を機に、うちもサテライトオフィスを各地に構えて、もっと地域に根ざして、地方の人たちと一緒に仕事をしようという機運が高まり、その第1号が東川町で実現するという一石二鳥になりました。
村山 かれこれ1年経ちますが、事務所の方々に変化は見られますか。
隈 現地での仕事を通じて、あるいは一住民として暮らす中で期待以上に地域の皆さんとの交流が活性化し、所員たちの文化まで変わってきている気がします。地域とともに未来をつくっていこう、皆さんと一緒に盛り上がろうといった気概や意欲は、都会の仕事場では表に現れなかったものです。


「勝つ建築」の持つ脆さと「負ける建築」にある強靭さ
村山 そうした都市から地方への軸足移動に加えて、隈さんは「小さな建築」とか「負ける建築」といった提言を発信されています。これは旧来の建築様式に対するアンチテーゼと受け止めてよろしいですか。
隈 私がこれを言い出したのは、阪神・淡路大震災や東日本大震災から得た教訓がきっかけです。20世紀の建築は、ひたすら強く大きなシステムを目指してつくられましたが、未曽有の災害の前にはなす術もない現実を突きつけられました。思い起こせば日本は、高度成長期に、いかに効率よく東京中心の大きなシステムをつくるかに腐心してきた、それがもはや限界にきていると思えてならないのです。
村山 大きなシステムによる「勝つ建築」は案に相違して脆さを露呈した……そう分かった以上、私たちは考え方を改めねばなりませんが、ではなぜ、小さなシステムによる「負ける建築」は強靭さを保持できるのでしょう。
隈 建築の目的を一言でいうと、内と外を分ける境界をつくることです。強い外力から内部を守るために、境目の壁を分厚くつくってはね返そうとする。それが「勝つ建築」の発想ですね。それに対して、初めから外力に抗おうとせずに、許せる限り内部へ受け入れる。つまり、ぎりぎりまで境界をなくしながら強靭さを確保し、なおかつ、外の世界と内の人間をつなげようとするのが「負ける建築」の考え方です。
村山 なるほど。境界を曖昧にする建築と聞いて、真っ先に思いつくのは伝統的な日本建築です。素材は何かといえば、木が頭に浮かびます。ただ、かつて日本で火事や地震への脆さゆえに木造建築が廃れた経緯を思うと、境界としての強靭さに不安はないでしょうか。
隈 実は、素材としての木の耐震・耐火性能に関する技術はこの20年間で飛躍的に進歩し、木造建築への抵抗感は希薄になっています。むしろCO2削減への貢献とか、人間のストレス緩和や集中力アップにもつながるなどの利点が見直されて、日本のみならず世界的に、木への移行が起こり始めています。
村山 そういえば、冒頭のシドニーの「The Exchange」も木が主役ですね。
隈 現在パリで進めている駅舎の設計計画でも、フランス政府の方針で内装のほとんどに木を用いています。もう少し大きな流れで建築を見ると、20世紀はコンクリートと鉄の時代で、それ以前はその場所特有の素材でつくられました。森が豊かな日本では木を多用し、ヨーロッパでは石やレンガを用いた。20世紀になると、人口が急増し、工業化も進んで、どこでも手っ取り早くつくれるコンクリートが好まれました。しかし私は今後、その場所に一番適した材料で、それぞれの個性をつくり上げる建築様式に回帰すると思います。
「断崖の町」の美術館が唯一無二のモニュメントに
村山 大システムから小システムへの流れでいうと、我々の電力業界にも、電源を大規模発電所に集約する従来の方式から、電力の地産地消に近い分散型電源へ移行する動きがあります。再生可能エネルギーの電源を拡充したり、CO2排出抑制技術に磨きをかけたりしながら、カーボンニュートラルな循環型社会へ着実に進んでいかねばなりません。
隈 おっしゃるように、大から小への移行には、自然や環境との調和とか、人間性の回復といった根源的な要求が背景にあると思います。建築デザインにおいても、奇をてらって目立てばいいという姿形では受け入れられず、環境によくなじんで、コミュニティのシンボルになるような新しい造形が求められています。その意味では、建築の再定義とか、都市の再デザインが始まっていると思います。
村山 それこそが隈さんの建築作品の本領かと思いますが、例えば、スコットランドのダンディーという町につくられた美術館などは、思いも寄らぬ造形美に目を奪われるだけでなく、そこに落とし込まれた歴史的背景や町の人たちの思いなどを知れば知るほど、見る者に親しみや愛着をもたらす作品ですね。
隈 ありがとうございます。あの町は海岸沿いの断崖と洞窟が名所になっていますが、国内でもあまり認知されていない存在でした。ところが2018年に「スコットランドの新しいランドマークに」との使命を帯びて設計した美術館が完成するや、地域住民から愛されて評判が評判を呼び、米国の著名新聞で「今年行くべき世界の旅行先」に選出されるという光栄にも浴しました。
村山 その土地に根ざした文化や風物から的確に造形を引き出すことで、唯一無二の建築が完成するということでしょうか。それから、うろ覚えの知識で恐縮ですが、古い発電所をリノベーションした美術館があるという新聞記事を読んだのですが……。
隈 恐らくそれは「テート・モダン」というロンドンの国立美術館ではないかと思います。発電所は内部の大空間を活かして、古風で味わいのある施設に改築される例が珍しくありません。私も中国・上海で古い造船所の建物をコンベンションセンターにつくり替えたことがありますが、歴史的建造物を安易に壊さずに再生利用するという、やはり世界的な流れがありますね。
村山 今のお話で思い出しましたが、かつて私が発電所の視察で北欧などの環境先進国を訪れた際、建物の形状や色使いが日本とは大分違っていて驚きました。それに刺激されて、当時、リプレースを控えていた磯子火力発電所や橘湾火力発電所のデザインや色合いを決めるにあたって参考にしました。周辺環境に溶け込み、あまり出しゃばらず、ただし無味乾燥ではないといった、時代に先駆けるデザインを採用したつもりです。
隈 おもしろいもので、その時代で最も機能的な形を追求した建築デザインには、くっきりと時代性が映し出されます。一見、無個性のようでいても時代の空気が感じられるので、発電所の建物もちょっとした工夫で魅力的なものにできるはずです。

エネルギーを原理にして都市の形を決める時代
村山 いま私たちが直面する様々なエネルギー問題にどう向き合っていけばいいのか、何か提言などがあれば最後にお聞きしたいのですが。
隈 エネルギーは、地球環境と最も密につながっているものという認識がまず大事です。都市の形成過程を見ると、古来、人々がどういう便利さを求めたかで都市の形が決まってきたわけで、20世紀は自動車などの交通インフラで都市の形が決められ、それによって人間の生活も規定されました。そして21世紀、これだけ地球環境問題が大きくなって、今度はエネルギーが都市の形を決める時代が来ているように思います。
村山 つまり、エネルギーを原理にして都市や建築を考え直したり、人間のライフスタイルを見直したりする必要があるだろうと……。
隈 さもないと人類がサステナブルに続いていけないという危機感を、誰もが共有しなければなりません。しかし残念ながら、都市デザイナーや建築デザイナーの現場でも、初めに形ありきでプランを立てて、後からエネルギー調達を考えるみたいな逆順が未だに起こりがちです。
村山 電気はどこか遠くから運んでくるものという考えは、たしかにサステナビリティに欠けるかもしれません。いまや自前の発電設備によって電気を自給自足することも可能で、地域単位でエネルギー需給をやり繰りする仕組みもつくれる時代ですから、都市計画や建築にまつわるエネルギー調達にも多様な選択肢があると思います。
隈 エネルギーは自分の暮らしと不可分のもので、その使い方しだいで地球環境を壊す方向にも、逆に守る方向にも振れていきます。自らの選択の結果がエネルギーと環境の問題となって眼前に現れる……そういう当事者意識を常に持つことが求められているのではないでしょうか。
村山 問題の解決を他人任せにしてはならない……そうと頭で分かっていても、なかなか行動が伴わないというジレンマを抱えた人も多いかと思います。これまでのお話を通じて、当事者意識を育むための良い処方箋はないものでしょうか。
隈 先の東川町のケースのように、都会から地方に出て、豊かな自然の中で暮らすことが当事者意識を増幅するのに役立ちます。多少の不便を強いられても、常に自分の命と向き合っている一種の緊張感を保つことが根源的に大事で、都会暮らしでは得られない利点だと思います。
村山 お話の一つひとつが、これからを生きる糧になった気がいたします。本日は、ありがとうございました。
(2023年2月21日実施)
構成・文/内田 孝 写真/吉田 敬
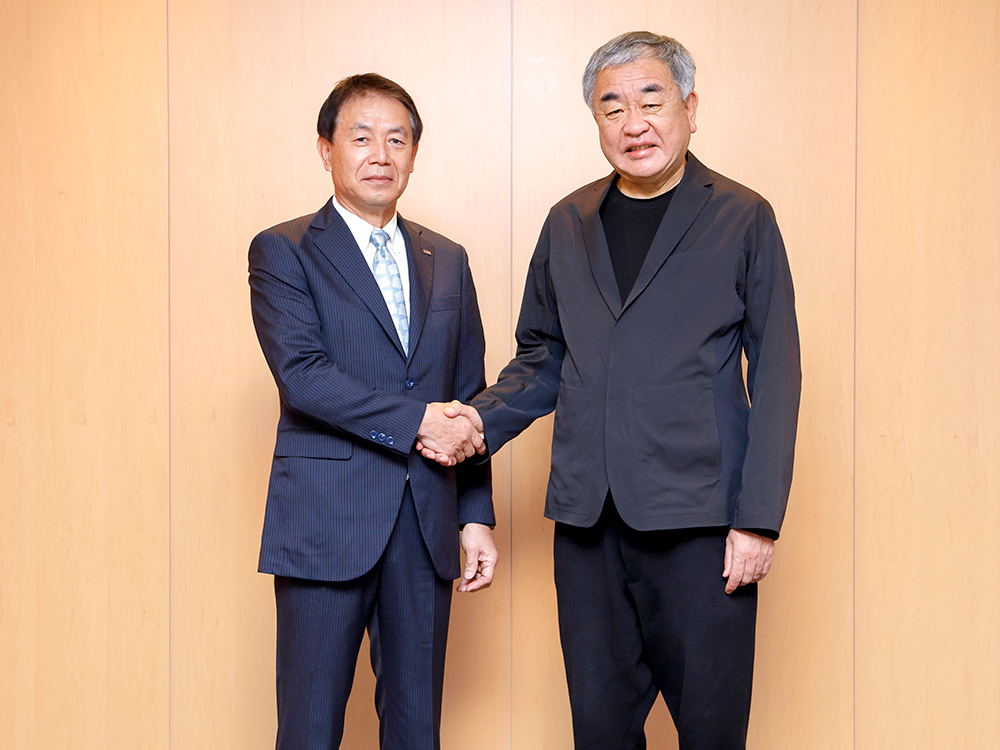

PROFILE
隈 研吾(くま・けんご)
建築家。1954年、神奈川県生まれ。東京大学大学院建築学専攻修士課程を修了。在学中にアフリカのサハラ砂漠で集落の美と力に目覚める。1990年、隈研吾建築都市設計事務所を設立。30を超える国や地域でプロジェクトを進行中。その土地の環境・文化に溶け込む建築を志向し、ヒューマンスケールのデザインを提案。木材など古来の素材を活かした「和」のデザインが持ち味。米国コロンビア大学大学院講師、慶應義塾大学教授、米国イリノイ大学客員教授などを経て現在、東京大学特別教授・名誉教授。主な著書に『全仕事』(大和書房)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)など多数。


