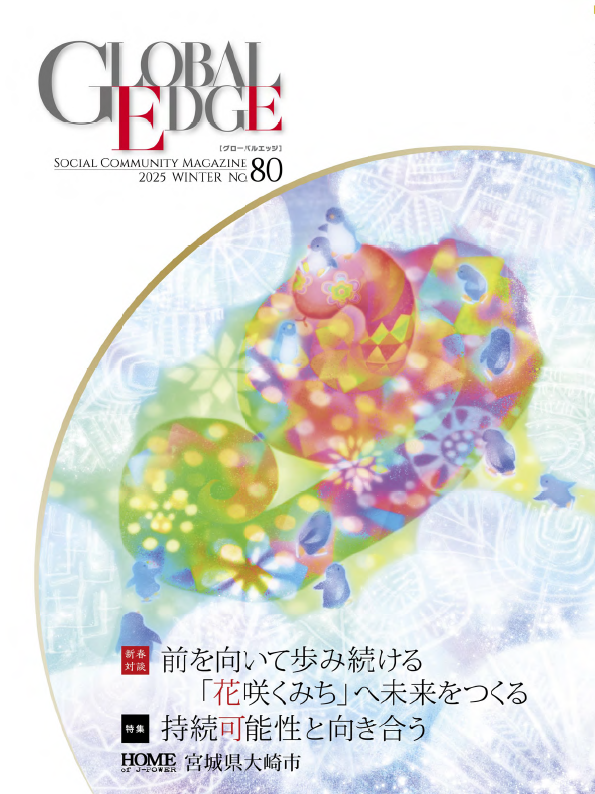伝統の樺細工技術を未来に伝える
株式会社八柳
匠の新世紀
株式会社八柳
秋田県仙北市

秋田県仙北市角館(かくのだて)。
江戸時代の武家屋敷が今も残るこの町の名産品が樺細工(かばざいく)だ。
山桜の樹皮の風合いを活かした樺細工の伝統を未来に残そうと努力する人々がいる。
創業140年を超える老舗製造元、株式会社八柳(やつやなぎ)を訪ねた。
江戸時代から続く伝統工芸技術を継承

代表取締役
八柳 浩太郎さん
樺細工は、秋田県角館に江戸時代から伝わる伝統工芸品だ。樺とは山桜のことで、万葉集などでは「かには(迦仁波)」と書かれていたが、後に「かば(樺)」に転化したものと言われている。磨き上げた樺を貼った茶筒などが有名で、温かみを感じる見た目が特徴の、古くから親しまれている日本を代表する伝統工芸品といってもよい。この伝統技法を現在も受け継ぎ、製造販売を続けている株式会社八柳の代表取締役 八柳浩太郎さんにお話を聞いた。
「樺細工は、江戸時代中期に佐竹北家の藤村彦六という武士が、秋田県北部の阿仁(あに)地方から角館に伝えたのが始まりで、その後下級武士の手内職として広まったと言われています。当時は薬などを入れる薬籠などをつくっていました」
その後、明治期になると職を失った武士たちが本職として樺細工をつくるようになり、当地の地場産業となった。全国的に知られるようになったのは、大正から昭和期にかけて問屋制度によって全国への流通ができたことと、「日本各地の民芸品の中にこそ美がある」として、職人たちによる素朴な工芸品を礼賛する「民藝運動」を展開した柳宗悦(やなぎむねよし)などが樺細工を優れた民芸品として紹介したことによるという。昭和の初期には茶筒や胴乱(煙草入れ)、文箱などの樺細工が全国に知られるようになった。
八柳は、1876年(明治9年)創業で、浩太郎さんで7代目、140年を超える歴史を持つ。
「創業当時は、仕出し屋や下駄屋などもやっていたようですが、3代目の時に樺細工専門になり、下駄屋だった経験を活かして、樺細工を施した樺下駄を製作し、当社だけのオリジナル製品として好評を得ました。昭和初期には秋田市の百貨店に売りに行っていたようです」
この樺下駄がよく売れ、昭和20年代以降の高度成長期には年間1万足以上も出荷。現在でも販売している八柳のロングセラー商品となっている。



樹皮の味わいを活かした削りと貼りの繊細な作業




樺細工は、大きく「型もの」、「木地もの」、「たたみもの」の3つに分類される。
型ものは、木型に合わせて芯になる材料をつくり、その上に桜皮を貼り付けて、筒状のものをつくる技法で、古くは胴乱や印籠、現代では茶筒がつくられている。
木地ものは、下地に木材を使ったものに桜皮を貼ったものの総称で、文箱や硯箱、宝石箱など箱形のもの。そのほか、テーブルや茶箪笥なども木地ものとされる。
たたみものは、何枚も貼り重ねて数cmの厚さを出した桜皮を作品に加工するもので、ブローチやペンダントなどの装飾品がつくられている。
そのつくり方は「型もの」を例に取ると次のようになる。
① 桜皮を山桜から採取。
② 桜皮を1~2年程度乾燥させる。
③ 桜皮を幅広の包丁で削り、0.3mmほどの厚さにする(樺削り)。職人が削ると光沢が出る。
④ 桜皮にニカワ(接着剤)を塗って乾燥させる。
⑤ 型の上に経木(きょうぎ)などを載せ、200℃程度に温めたコテを押し当てて成形する。
⑥ 成形した経木にニカワを塗り、温めたコテを押し当てながら桜皮を貼り付ける。ニカワとコテの温度が絶妙な職人技だ。
⑦ 部品を接着し組み上げる。
⑧ 研磨や塗装などの仕上げ作業。
主となる樺の磨きと貼り付けは、山桜の樹皮を約0.3mmの厚さまで削り、独特の光沢と味わいを醸し出し、それを木製の胴体にしっかりと貼り付ける繊細な作業だ。
こうした樺細工の製造工程は、多くの伝統工芸品がそうであるように、分業制で行われてきた。山桜の樹皮を採取する(樺はぎ)職人、樺削りをして樺を貼り付ける職人、仕上げを担当する職人、そしてアイテムを企画し販売する製造元(問屋)。
八柳は、主に商品を企画する製造元にあたる。1点ものの高級品は伝統工芸士と連携して製造、普及品は自社内で製造するほか、20人ほどの外部の職人と連携して作業分担しながら製造している。

ライフスタイルの変化に合わせつつ伝統を守る努力


樺細工は山桜の樹皮の特質から、防湿性や抗菌性があるとされ、古くは薬籠や胴乱、昭和以降は茶筒などが主な製品として生産されてきた。しかし、近年は一般家庭で茶葉からお茶を淹れて飲む人が減り、茶筒の国内需要は減っているという。こうしたライフスタイルの変化により、樺細工も売上げや担い手が減り、市場や環境が大きく変化していると浩太郎さんは語る。
「10年前は角館で5社あった製造元が今は3社になりました。また、山の仕事をする人が減ったので、山桜から樹皮を採取する『樺はぎ職人』がいなくなり、原材料である樺の入手が困難になりました」
こうした状況を改善するため、八柳では自社で樺の採取を行っている。
「樺はぎは、梅雨明けからの2カ月間しか行うことができません。この時期は、樹皮に水分が含まれ、樹皮を容易にきれいに剥がすことができますが、それ以外の時期は木が乾燥して樹皮を剥がすことが難しくなるからです。この周辺では8~9月がその時期になります。春のうちに、山桜がどこにあるかを確認しておき、山の所有者に許可を取って、8~9月に社員総出で樺はぎをしています」
山桜は樹皮を半分以上残せば枯れることなく、生き続けることができ、新しい樹皮を再生させる。山仕事をする人が減少し、山が荒廃、自然の山桜が減っているため、八柳では休耕地などを活用して山桜を植樹する活動も行っている。
さらに、職人自体のなり手も減っているため、職人を自社で育成する試みも始めている。
だが、八柳にとってもっとも大事なことは、「その時代その時代のライフスタイルに合わせたものづくりをすることだと思います」と
浩太郎さんは語る。
「下駄に樺細工を施したのも八柳のオリジナルでしたし、プラスチックなどの新しい素材に樺を貼ることや、スマートフォンケースを開発することなど、常に新しいことに挑戦してきたのが八柳の歴史です。そうした気風は商品開発だけでなく、戦前からすでに海外への販路を開拓していたことからも感じています」
伝統の中で新しい試みに挑戦してきたのが八柳の歴史であり、今も毎年5〜10アイテムほどの新製品を発表している。また、秋田県でデザインブランドを立ち上げた合同会社casane tsumugu(カサネツムグ)や外部デザイナーとのコラボにも積極的で、東京都内の百貨店にも毎年出店するなど来店者のニーズを探ることにも余念がない。インバウンドによる購入も売上げの約2割を超えた。
「先代が言っていたことですが、『伝統は絶えざる革新と絶えざる努力によって守られる』のだと思います」
時代時代に合ったものづくりをしながら、新製品を市場に提案していくことが伝統を守ることにつながっていく。こうした努力によって八柳の伝統はこれからも継承されていくことだろう。

取材・文/豊岡 昭彦 写真/斎藤 泉
PROFILE
株式会社八柳
1876年(明治9年)創業の樺細工の製造販売元。樺細工を代表する茶筒をはじめ、茶杓などの茶道具やテーブルウェア、文房具、インテリア雑貨、アクセサリーまで商品は多岐にわたる。樺細工を施した樺下駄は同社を代表するロングセラー商品。