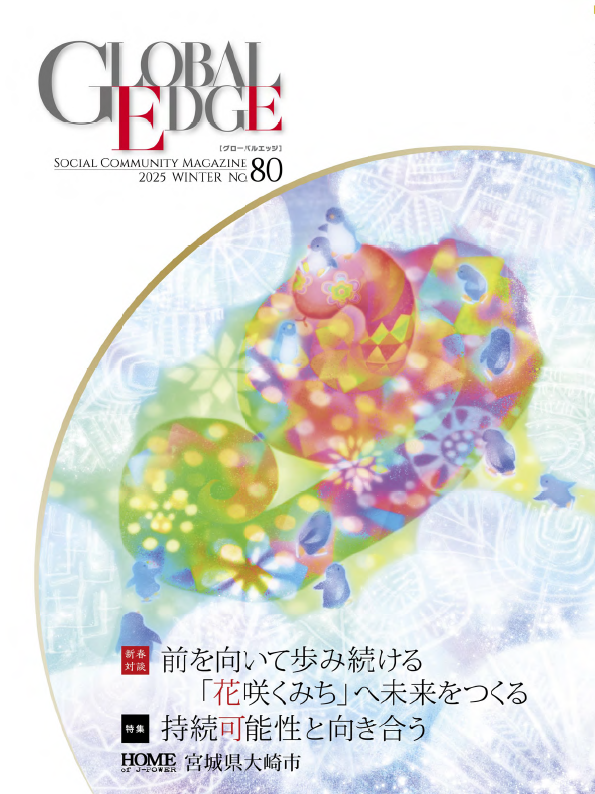人と木とをつなぐ架け橋に 樹木医が描く未来
片岡 日出美
Opinion File

祖母と歩いた山々から自然の偉大さを学ぶ
2024年9月18日の夕方、茨城県阿見町(あみまち)の鹿島神社に落雷があり、樹齢500年以上の御神木が焼ける火災が発生した。御神木の焼損は激しく、そのままにしては二次被害の危険がある。
町の文化財に指定され、地域のシンボルとして人々に愛されてきた御神木をなんとか守りたい。危険を除去しつつ、保全する方法はないだろうか。樹木医(※1)として、この御神木を、安全に守っていくために、いばらき樹木医会メンバーや研究者、行政担当者、地域の方々と協議し対策を講じてきた。
樹木医とは、その名の通り「木のお医者さん」。樹木の健康状態を診断し、治療にあたる専門家だ。片岡日出美さんは樹木医として、町の街路樹から山林の巨木まで様々な現場で木と向き合っている。その原点は、祖母との小旅行だ。
片岡さんは神奈川県川崎市生まれ。都市部のマンションで幼少時代を過ごした。幼い頃から喘息を患い、アトピーや鼻炎にも悩まされた。そんな様子を見かねて、祖母は週末ごとに近くの山に連れ出してくれたという。
「神奈川の相模湖や丹沢、東京の御岳山や高尾山、時には栃木の那須まで足を延ばすこともありました。山を歩くのがとりわけ好きだったわけではありませんが、祖母と週末に出かけることが楽しかったのです。自分が住んでいるエリアとは明らかに空気が違い、山や森林が空気をきれいにしてくれているのだと実感したのも、この頃だったと思います」
もう一つ忘れられないのは、小学校4年生の時、熱帯地域の森林破壊(※2)について学んだことだ。地平線の果てまで木が切り尽くされ、その一部が日本にも輸入されていること、プランテーションによる自然破壊や人権の問題……他国の資源を利用して自分たちが豊かになっていることに違和感を抱いた。
「子ども心に、これは絶対によくないことだと衝撃を受けたのを覚えています。これまで一貫して樹木と関わってきたのは、こうした幼い頃の体験があったからかもしれません」
大学では林学を専攻し、卒業後は大手林業会社へ。1年目から木材や建材の流通管理を担当した。当時まだ女性の総合職は少なく、片岡さんが配属された支店では初の女性総合職。先輩たちからは温かく、時には厳しく指導を受けながら、原木市場や港での輸入取引の現場などを飛び回った。グローバルな環境での仕事にやりがいを感じ、同期や先輩にも恵まれて充実した毎日を送っていたという。ただ、入社して3年が過ぎた頃、片岡さんの胸にある思いがよぎる。
「結婚を機に本社勤務となり、部署をまたいで様々な先輩や上司の話を聞く機会が増えました。心が躍るようなダイナミックな仕事の話を聞く一方で、定年を迎えたら、この仕事から離れなくてはいけないことに寂しさを感じたのです。定年は会社員の定めではありますが、人生をかけて関わってきた仕事を、いつか辞めなくてはいけないのだなと」
その後、長男を出産した片岡さんは、自分のキャリアと向き合って一つの結論を出した。
「会社員という形に縛られず、この後もずっと働き続けていくためには、専門技術を身につけ、それを裏付ける資格を持つことが重要だと考えました。そこで浮かんだのが、樹木医という仕事です。私たちの業界で一番難しい資格を目指してみようと思ったのです。夫も資格の必要な職業に就いていますが、彼の仕事の幅広さを間近で見て、資格を取ることの意義を感じたという側面もあります。彼ばかりいろいろな経験ができて、ずるいじゃないかと(笑)」
大手林業会社を退職した片岡さんは、造園業を手がける樹木医専門会社に転職。代表である女性樹木医の背中を見ながら、マンションの樹木の設計や個人宅の庭木診断などに携わった。現場で実務経験を重ねながら、樹木医の資格を取得したのは2017年。同じタイミングで樹木医に合格したのが、現在、片岡さんが取締役を務めるHARDWOOD(※3)株式会社の代表取締役である森広志さんだ。

樹木医の研修仲間と新たな挑戦へ
森さんとの出会いは、片岡さんがまだ最初の会社に勤務していた頃。林業に携わる20代、30代の若者が集まる「若手林業ビジネスサミット」(※4)で林業の未来について語り合った仲間だった。その数年後、樹木医を目指す人のための研修で再会し、同じ年に2人とも見事合格したというわけだ。
「樹木医の試験は毎年1回あって、合格するのは100人くらい。合格者は2つのグループに分かれて2週間の研修を受けます。私は森と一緒のグループでした。その研修では朝から夕方まで座学や実習がみっちりあり、毎日試験を課されました。非常にハードに鍛えられる2週間ですが、その分、同期の結束も強くなるんです。のちに、一緒に会社を立ち上げたメンバーは、森を含め、皆この研修で苦楽をともにした仲間です」
樹木医になったばかりの頃、片岡さんはまだ樹木医専門会社で働いていたが、スタッフは女性が多く、樹木の治療や施工には一緒に作業をしてくれる仲間が必要だった。そんな時、研修で一緒になった森さんに声をかけたのだという。林業の現場経験が豊富で、樹木医という視点でも作業をしてくれる森さんは、頼りになる存在だったのだ。
「いわゆる正解のない施工に何度も取り組むうちに、信頼関係が強まっていきました。やがて、それぞれの専門性を補完し合いながら仕事ができれば、この先もっと飛躍できるのではないかと考えるようになったのです」
その思いが形になったのが、HARDWOODという樹木のスペシャリスト集団だ。


企業の森づくりや地域再生にも貢献
HARDWOODが手がける事業は多岐にわたる。樹木医の科学的知見と精密機器を使った診断に基づいた治療、クレーンやレッカーを使わない特殊伐採(※5)、森林の調査、公園や植物園といった施設の設計なども事業範囲だ。
「街路樹が突然倒れて驚いたという話を聞きますが、多くの場合その兆候はあります。樹木医はその異変を適切に把握し処置ができるよう、日々研修を受けトレーニングしています。例えば以前、車がぶつかり樹皮がはがれてしまった街路樹を診断したことがあります。樹皮だけでなく内側の形成層もむけてしまって、今後が憂慮される状況でした。というのも、木は数mmの薄さしかない形成層から水分を吸い上げ、葉っぱで光合成した栄養分を運ぶ構造のため、形成層が傷つくと木の成長に深刻な影響を及ぼします。仮に木の内部に空洞ができれば、強度を保つことができず、幹が折れてしまう懸念も出てきます。こうなると、外側からはうかがい知れない内部も含め、木全体の状態を正しく診断し、適切な治療を施すことが必要になってくるのです」
HARDWOODはほかにも、企業の森づくり事業の支援を手がけることもある。日本郵船株式会社の「ゆうのもりプロジェクト」では、森づくりを行う地域の選定から整備計画の策定、現場での実地作業までを担っている。また、自治体からの依頼も多く、高知県梼原(ゆすはら)町では地域林政アドバイザーとして公園の再生事業を手がけている。さらに、子どもたちへの環境教育活動、樹木医としての働き方やキャリアに関するセミナー活動、SNSによる情報発信など、自然環境への理解を深めるための活動、林業や造園業を啓蒙するための活動にも力を入れている。
木の声を聞き豊かな未来をつくる
林業と造園業(※6)は、どちらも木を扱う仕事でありながらまったく異なる分野だ。森さんは林業から、片岡さんは造園業の視点から個々の課題にアプローチする。実はこうした2人が肩を並べて取り組む会社はそう多くないそうだ。
「森は林業出身なので、木を更新させながら利用していく意識が高い。私は木を守りたいというスタンスで臨みます。そんな2人がタッグを組むことで、相乗効果が生まれたらと期待しているんです」
作業効率から考えれば切ったほうがいいと思える枝でも、例えばそこに住んでいる人が、その枝が1本あることで日陰を得られたり、木との距離が近く感じられたりする場合もある。そういうケースにおいて、科学的な根拠をもって、安全に木を残す判断をできるようになりたいという。
「その枝から得られる喜びや癒やしは、効率化、合理化という概念を凌駕するものだと思います。樹木医として、危険度の診断をするだけでなく、心身の健康への寄与、景観向上、騒音対策、エネルギーコストへの効果なども丁寧に説明を繰り返していく必要があると考えています」
でも、こうした仕事運びができるのは、森さんの林業の知見に基づいた柔軟な現場力があればこそ。一見、相反する立場に見える両者の思いが掛け合わされ、唯一無二の仕事を実現している。
今、人の生活と森林は遠くなりすぎてしまった、と話す片岡さん。国土の3分の2を森林が占める日本(※7)で暮らしながら、私たちはその資源について知らないことが多い。
「知らないということは、未来に対する展望を描きにくいということ。それは大きな課題だと捉えています。私たち樹木医は、この樹種のこの状況であれば、例えば数年後はどのくらいのサイズになるのか、どのような林相に遷移していくのかなど、経験からある程度予測することができます。つまり、木や森林の代弁者となり得る。そのような立場から、人と木、人と森林をつなぐ架け橋になれたらと思っているんです」
木の声を聞き、それが発する違和感を捉え、次世代につなげていく。人々がより豊かな人生を送るために、樹木医としてできることがもっとあるはず――そんな信念を胸に、今後は医療やアート、AIなど異業種や新技術とのコラボレーションも積極的に進めていきたいと意気込む。目の前に立ち塞がる課題に挑むには、業界を超えた連携が必須だからだ。「生涯、木に関わっていきたい」と話す片岡さん。
「木を治療することで花付きがよくなったり、お客様が喜んでくれることが何よりもうれしく感じます」
小さな幸せの積み重ねが、持続可能な社会をつくる大きな力となる。

取材・文/脇 ゆかり(エスクリプト) 写真/竹見 脩吾
KEYWORD
- ※1樹木医
一般財団法人日本緑化センターが認定する資格。街路樹や庭木、天然記念物の樹木などの診断、治療、保全を行う。樹木医の認定者総数は3,272名(2023年12月現在)。 - ※2熱帯地域の森林破壊
人口増加に伴い、食料確保のために森林を伐採して農地や牧草地に転用したことで熱帯林が減少。温暖化加速の原因ともなるため、熱帯林の保護は喫緊の課題となっている。 - ※3HARDWOOD
社名は広葉樹(hardwood)から。日本では広葉樹はあまり産業に活用されておらず、管理が行き届かずに荒廃する広葉樹の山は少なくない。広葉樹の課題と向き合う姿勢を社名に託している。 - ※4若手林業ビジネスサミット
「林業で生きる」ことを目指す若者が集まり、開催地の林業の取り組みを見学し、林業について参加者同士で語り合う3日間のイベント。参加は30代まで。 - ※5特殊伐採
高木や巨木を根元から倒すのではなく、樹上に登ってロープなどを使い伐採すること。狭い敷地内で根元から伐採すると周囲の建物や送電線を傷つける恐れがあるため、この方法が採られる。 - ※6林業と造園業
林業は森林で育成した樹木を伐採し、それを加工して製品をつくる。対して造園業は、公園や個人宅などの造園空間を設計、管理、施工する。 - ※7日本の森林
日本の森林面積は約2,502万haで、国土の67%を占める(2022年、林野庁)。先進国(OECD諸国)の中で森林面積率は第3位、日本は世界有数の森林大国といえる。

PROFILE
片岡 日出美
HARDWOOD株式会社取締役
かたおか・ひでみ
1986年、神奈川県生まれ。筑波大学生物資源学類では日本林業の社会経済学を専攻し、卒業後は住友林業株式会社の木材流通部門に勤務。結婚・出産を機に樹木医を目指し、都内の樹木医専門会社に転職。2020年、林業出身の森広志さんとHARDWOOD株式会社を設立、取締役に就任。都市の樹木の診断や治療、民間緑地の管理のほか、大手企業の森林活動の支援や、地方行政の地域林政アドバイザーなども務める。2022年、茨城県森林審議会委員に就任。現在、12歳、10歳、8歳の3児の母。