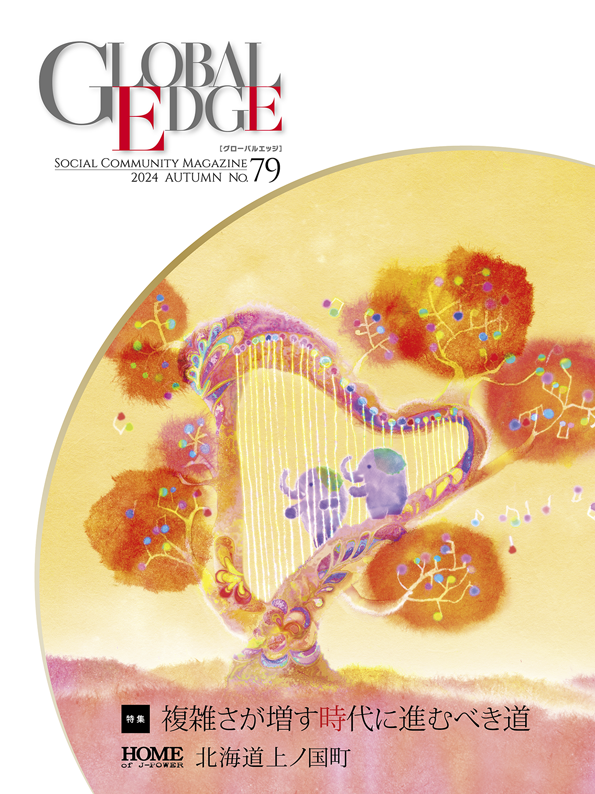伝統に新しい風を吹き込む老舗酒蔵女将の挑戦
西山 桃子
Opinion File

高浜虚子に救われて文人墨客の交流の場に
「酒もすき餅もすきなり今朝の春」と詠んだのは、明治から昭和にかけて活躍した近代俳句の巨人、高浜虚子(※1)だ。諧謔(かいぎゃく)味のある酒の句を残している虚子だが、彼がこよなく愛した酒蔵がある。美しい山々に囲まれた兵庫県丹波の地に1849年(嘉永2年)に創業した株式会社西山酒造場だ。
明治生まれの3代目蔵主の西山亮三さんは「泊雲」の号を持つ俳人であり、虚子の一番弟子として知られている。大正の初めに家業が傾きかけた際、窮地を救ったのはほかならぬ虚子だった。西山酒造場の日本酒を「小鼓(こつづみ)」と名づけ、主宰していた俳句雑誌『ホトトギス』(※2)で大々的に宣伝したことで、新たな顧客を得ることができたのだ。それ以来、虚子をはじめ多くの文人墨客が西山酒造場を訪れ、文化サロンとしても賑わった。そこから1世紀の時を経て、伝統のバトンを受け取ったのは、西山酒造場の女将(おかみ)、西山桃子さんだ。
西山桃子さんは大阪府堺市生まれ。短大を卒業後、銀行員として働いていたが、子どもの頃からの夢だった看護師になりたいという思いが再燃し、看護専門学校へ。もともと喘息の持病があり、身近に接していた医療従事者への憧れを捨てることができなかったのだ。晴れて看護師として働くことになったが、西山酒造場6代目蔵主となる西山周三さん(現代表取締役社長)との結婚を機に丹波で暮らすことに。
「結婚当初、私は大阪の病院で働いていました。いわゆる別居婚です。夫も5代目である義父も、私のキャリアを尊重してくれました。でも、第一子を妊娠中に、長く勤めていた番頭さんが病に倒れて退職し、経理を担う人がいなくなってしまって。そこで、元銀行員である私が手伝うことになったのです」
丹波を訪れたのは結婚の挨拶(あいさつ)に行ったのが初めて。実はその時に、ある洗礼を受けた。
「反対車線を走っていた車が鹿とぶつかったのを目撃したのです。ドーンという大きな音がして、見るとその鹿は、私が奈良公園で見るのとはまったく別の動物でした。大きな体に立派な角、もう山の神様といった風情で(笑)」
自分はこういう場所に住むんだなと思ったのが、丹波の第一印象だったと微笑む。しかし、実際に暮らし始めると、その豊かさにすっかり魅入られてしまった。
「自然が豊かで空気がきれい。地下10mから汲み上げる井戸水は超軟水でとてもおいしいですし、近くの有機農家さんは毎日のように採れたての野菜を分けてくださいます。四季折々の美しさを感じながら、人として豊かな生活ができる場所だと実感しました」
大阪で満員電車に揺られていた頃には得られなかった確かな豊かさがここにはある。丹波で暮らし始めてから、喘息の症状はまったく出なくなったそうだ。

日本酒業界は右肩下がり 女将の奔走が始まる
西山酒造場の経理を担当するうちに、西山さんは、酒づくりに対するリスペクトの気持ちが高まっていった。重たい米を運び、冬の寒い時期に冷たい水で米を洗い、発酵というコントロールが難しいものと向き合いながら長い時間をかけて酒づくりに挑む。間近で見る杜氏や蔵人たちの丁寧な仕事ぶりには感動を覚えたという。
一方で、日本酒を取り巻く外部環境は決して明るいものではなかった。アルコール飲料の消費量は減少傾向、特に日本酒の消費量が減り、日本酒の国内出荷量(※3)は1973年(昭和48年)のピーク時約177万キロリットルの3分の1、約59.3万キロリットルにまで落ちこんでいた(2010年当時)。実際に、初めて自社の決算書を見た西山さんは驚愕する。
「果たして3カ月後、この酒蔵は残っているのだろうか……」
危機感を募らせた西山さんは、経理担当の枠を超え、財務、広報、営業、人事、教育と「できることは何でも担う」女将として奔走する日々が始まった。
「丹波の人たちは奥ゆかしいというか、自分たちの仕事にプライドを持って酒づくりに勤(いそ)しんでいるのに、商売の話になると不得手な印象がありました。みなさんの仕事ぶりも商品も極めて素晴らしい、そのことはもっと評価されるべきだし、世の中に伝えるべきだと思う。そう蔵人たちに話し、まずは蔵人の意識を変えるところから始めていきました」
外の世界から飛び込んだ西山さんだからこそ、見えることも多かった。丹波で暮らすようになった時、国の登録有形文化財に指定されている蔵や母屋を見て素敵だなと思っていたが、家族にとっては「ただの古い建物」。老朽化しているので新しくつくり替えたらいい、という発想に驚くと同時に、こんなに歴史ある貴重な建物は絶対に残さなくてはいけない、と心に誓ったという。
女将としてやりたいこと、やるべきことが山積していく中、2014年8月17日、転機となるできごとが起こる。


地域のため社会のために酒蔵ができること
未明から降り続いた豪雨により、丹波市内で大規模な土砂災害が発生した(※4)。四方の山が崩れ、西山酒造場には大量の土砂が押し寄せた。倉庫には1mを超える泥が流れ込み、酒米や商品は廃棄処分。酒づくりは休止せざるを得なくなった。そんな窮状を救ってくれたのは、大勢のボランティアだった。
「お盆後のうだるような暑さの中、次第に固まっていく泥を、みなさん懸命にかき出してくださいました。幸いにも井戸は無事でした。これは神様から酒づくりを続けなさいと言われているのかなと思いました」
ボランティアの力を借りて、被災から3週間後には醸造を再開することができた。この経験を経て、西山酒造場の酒づくりは大きく変化していく。
「これだけの被害に遭いながら復興することができたのは、人の縁のおかげです。ボランティアとして、古くからのお客様も手伝いに来てくださいました。『おじいちゃんが好きだったお酒だから』とおっしゃる方もいて、こうしたご縁によって私たちは助けられたのだと実感しました。私にとっても蔵のみんなにとっても、人生観が変わるできごとでした」
これまでは旨い酒をつくることばかりを追求してきたが、これからはそれだけではいけない。地域のために、社会のために、酒蔵として何ができるのか。自然とそんな気持ちが湧き上がったのだという。
「過疎化が進むこの丹波の地で、酒づくりという伝統産業を次世代につなげることで、貢献できることがあるのではないかと考えました」
被災後は、日本酒づくりを学ぶ人を受け入れる教育機関としての活動をスタートした。海外からも酒づくりについて学ぼうと多くのソムリエ(※5)が西山酒造場の門を叩く。地元の小学生には、酒米づくりから日本酒ができるまで、1年を通して学ぶプログラムを提供する。丹波の自然の恵みを活かしたものづくりを体感し、地元に誇りを持ってほしいという願いから生まれた企画だ。商品開発においては日本酒だけにこだわらず、リキュールや蒸留酒に加え、米の発酵技術を活用したノンアルコールの甘酒ヨーグルトも手がけている。
酒づくりの歴史や発酵の文化、丹波の素晴らしさを伝えたいという西山さんの思いが実を結び、この夏、酒造場内にオープンしたのが複合施設「鼓傳(こでん)」だ。1896年(明治29年)に建てられた木造の酒蔵をリノベーションしている。あえて古い建物を残したのは、酒づくりの歴史の息吹を多くの人に体感してほしいという西山さんの願いがこめられている。
1階のカフェでは、丹波の有機野菜を中心に白砂糖を使用せず麹の旨みを生かした発酵食が提供される。蔵人の「発酵まかない食」が楽しめるというコンセプトだ。酒樽の一部が客席に使われるなど、往時の酒蔵の痕跡を探すのも楽しい。2階はギャラリーと宿泊施設。ギャラリーには高浜虚子をはじめ、小鼓のロゴやボトルのデザインを手がけた綿貫宏介(※6)など西山酒造場にゆかりのあるアーティストの作品が並ぶ。宿泊は1日1組限定で、蔵人とともに酒づくりを体験することができる。
西山酒造場が持っている資源を活かして、できることがあるなら何でもトライしたいと話す西山さん。今後キーとなるのは「観光」だと考えている。
「丹波の土地の魅力と西山酒造場というリソースは、充分な観光資源になると思っています。中長期的には、事業の大きな柱として観光業を視野に入れています。それは、過疎地域の問題を解決する糸口になるかもしれませんし、衰退産業である酒造業の未来を照らす光になるかもしれない。そんな期待を抱いています」
脈々と続いてきた伝統のバトンを受け継いだ自分たちが、次にバトンをつなげるためには何をすべきなのか。常に未来のことを考えながら進むべき道を決めていきたいと話す。
「私は銀行員としてお金にからむ人間の様々な側面を見、看護師として人の生死に立ち会い、今はお酒に携わっています。最終的に、世の中に必須のものではないお酒にたどり着いたことには、何か意味があるのではないかと感じます。
小鼓シリーズに『路上有花(ろじょうはなあり)』という商品があるのですが、ボトルのデザインをした綿貫宏介は『道端に1本の花が咲いていて、酒があればそれでいい』という考え方の人でした。お金でもなく、生命の長さでもなく、大切なのは今を精いっぱい生きること。そんな思いに至るよう、導かれてここまで来たのかなと思うんです」
看護師の仕事について尋ねると、「医療ドラマを見ると、ちょっと戻りたくなることもあるんですよ」と笑う西山さん。
「でも、丹波地方の酒蔵の女将という場所を与えられたのであれば、そこで役割を果たすことが、私にとっての幸せです」
高浜虚子は「古壺新酒(ここしんしゅ)」という造語を残している。俳句とは「古い壺(形式)に新しい酒(花鳥諷詠の新しい内容)を盛るものだ」という考え方だ。まるで、西山さんの女将としての挑戦そのものに思えてくる。時を経て、虚子は再び、丹波の酒蔵にエールを送っているのかもしれない。



取材・文/脇 ゆかり(エスクリプト) 写真/吉田 敬
KEYWORD
- ※1高浜虚子
愛媛県出身の俳人。尋常中学校で河東碧梧桐と出会い、碧梧桐を介して正岡子規に俳句を学ぶ。自然界の現象を重視した花鳥諷詠を句の基本とし、多くの俳人を指導した。 - ※2ホトトギス
1897年(明治30年)に正岡子規の友人である柳原極堂によって松山で創刊された俳句雑誌。のちに高浜虚子が引き継ぎ東京で刊行。夏目漱石が『吾輩は猫である』を発表したことでも知られる。 - ※3日本酒の国内出荷量
日本酒造組合中央会の調査によると、日本酒の国内出荷量は、1973年のピーク時には170万キロリットルを超えていたが、その後減少に転じ、2023年にはおよそ39万キロリットルに。 - ※4丹波市の豪雨
西山酒造場がある丹波市市島町を中心に土砂災害や洪水による被害が発生。全壊家屋18戸、半壊・一部損壊家屋52戸、床上浸水169戸、床下浸水784戸と甚大な被害をもたらした。 - ※5ソムリエ
客のニーズに合わせてワインを選び、サービスをする専門職。西山さんによると、ヨーロッパでは大吟醸を知らないとトップのソムリエにはなれないのだとか。 - ※6綿貫宏介
書画、陶磁器、ガラスなどの分野で作品を残した芸術家。5代目の裕三さんは綿貫の世界観に魅せられ小鼓のロゴやボトルなどのデザインを依頼。まったく新しい日本酒の意匠が完成した。

PROFILE
西山 桃子
株式会社西山酒造場
取締役女将
にしやま・ももこ
1975年、大阪府生まれ。短大を卒業後、銀行に就職。幼少の頃から喘息の持病があり、医療従事者の献身的な姿に憧れを抱いていたこともあって、銀行を退職し看護専門学校へ。2007年、西山酒造場6代目蔵主となる西山周三さんと結婚。数年後に丹波市に移り住む。酒蔵の経理担当者が不在になったことから看護師の仕事を辞め、経理を手伝うことに。酒蔵の経営状況の厳しさを痛感し、女将として経営を含めあらゆる業務を担うようになる。過疎化が進む地元丹波を盛り立てようと、酒蔵を拠点に様々なサービスを提供。8月にオープンした複合施設「鼓傳」は、その集大成ともいえる。