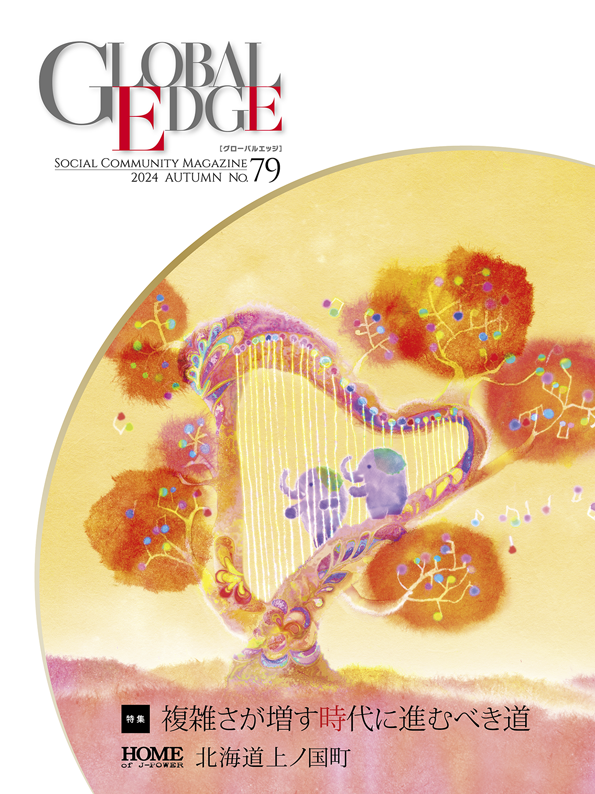エネルギーにおける哲学と技術基盤の必要
―― J-POWER民営化20年に寄せて ――
寺島 実郎
Global Headline
J-POWERが2004年に民営化して20年が過ぎた。J-POWERは、第2次世界大戦後の電力不足を補うため、大規模水力を開発する国策会社として設立されたが、21世紀になり、世界的なグローバル化の流れと、競争力を身に付けるため完全民営化の道を選んだ。それからの20年はエネルギーを取り巻く環境が激変した時代であり、J-POWERにとって「試練と苦闘の20年」だったのではないかと想像する。
いうまでもなく、この20年に大きなインパクトを残したのは、東日本大震災と気候変動問題だ。
J-POWERが民営化した2004年当時、CO2排出量が少なく、発電コストも安いことから、政府が「これからは原子力の時代」と強調、「原子力ルネッサンス」と言われた時代だった。だが、2011年の東日本大震災と、それに伴う原子力発電所事故が起こり、世論は原子力反対、再生可能エネルギー礼賛へと急激に方向転換する。2012年に導入されたFIT(電力固定価格買取制度)を活用して、一儲けしようという企業が太陽光発電に雪崩を打って参入したのがこの時代だ。
その後、2022年にウクライナ戦争が起こり、エネルギー価格が高騰、脱原発をうたっていたドイツがエネルギー政策の転換を迫られるなど、世界的にもエネルギーを取り巻く環境は混乱している。
私は、ことエネルギーについては、流行に惑わされてはならないと考える。エネルギー戦略は、特に日本においては、絶妙のバランス感覚と、技術の粘り強い蓄積が必要であり、ある種の哲学が求められる。なぜなら、外国との間に一本の連系線も持たず、自国内で電力供給を完結しなければならないからである。
私の認識では、J-POWERは化石燃料利用の効率化や環境との共生に本気で取り組んできた企業の一つと言ってもいい。石炭ガス化を徹底的に研究し、石炭火力で世界最高レベルの効率化を達成するとともに、そこから水素を取り出す技術も開発。将来的な大規模水素利用にも貢献していくことだろう。
また、利益の出なかった風力発電に民営化前から取り組み、風力の知見を蓄積した上で、これから始まる洋上風力発電所建設にも本格参入していくと聞く。さらに地熱についても他に先んじて大規模発電所を開拓してきた。ASEAN諸国をはじめ、世界各地で発電を行っていることも特筆に値する。
エネルギー関連の技術は、一朝一夕に積み上げることはできない。不断の努力とたゆまぬ研究開発によって技術基盤を高め、様々なプロジェクトを打ち出し、電力の安定供給を続けるJ-POWERが「試練と苦闘の20年」を超えてさらなる成長を遂げることに期待したい。
(2024年8月20日取材)
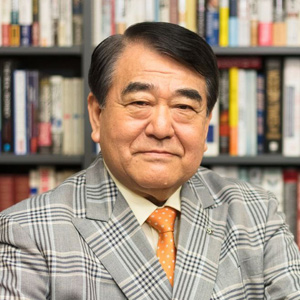
PROFILE
寺島 実郎
てらしま・じつろう
一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長。1947年、北海道生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、三井物産株式会社入社。調査部、業務部を経て、ブルッキングス研究所(在ワシントンDC)に出向。その後、米国三井物産ワシントン事務所所長、三井物産戦略研究所所長、三井物産常務執行役員を歴任。主な著書に『21世紀未来圏 日本再生の構想──全体知と時代認識』(2024年、岩波書店)、『ダビデの星を見つめて 体験的ユダヤ・ネットワーク論』(2022年、NHK出版)、『人間と宗教あるいは日本人の心の基軸』(2021年、岩波書店)など多数。メディア出演も多数。
TOKYO MXテレビ(地上波9ch)で毎月第3日曜日11:00〜11:55に『寺島実郎の世界を知る力』を放送中です(見逃し配信をご覧になりたい場合は、こちらにアクセスしてください)。