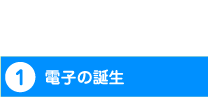
液体につけた亜鉛板が溶け始め、小さな泡が発生します。このとき亜鉛イオンと電子が生まれます。
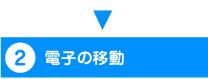
亜鉛イオンは溶液の中に溶け出し、電子はリード線を通って銅板の方に動きはじめます。
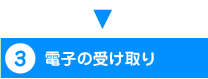
銅板に移動した電子は溶液のなかにある水素イオンとくっついて、水素ガスに変化。ガスは小さな泡となって銅板の表面にくっつきます。(あまりに小さくてその泡を実験班は見落としていました)水素は亜鉛よりもイオンになる力が弱い。だから電子とくっつき水素ガスにもどる。電子とくっつきたい水素イオンは次々と、電子を受け取り、亜鉛板は電子を送る。こうして電気が流れる。
|

