|
●それでも電球はつかないの?
電気はつかないんですか? 1000分の1秒とはいえ、800ボルトですから電球が光ってもいいはず。たとえばカメラのストロボみたいに…。そんな質問に館長さんは丁寧に答えてくださいました。「残念ですが、電気うなぎの出す電気は非常に大きいのですが、あまりに一瞬すぎてそのままでは電球を光らせることはできません」と館長さん。そして「そのままでは無理ですが、ある方法でその電気を楽しむ方法があるんですよ」と教えていただきました。
●電気うなぎのクリスマスツリー
マリンピア松島水族館では実際に発電する魚を見てもらうために、クリスマスシーズンに電気うなぎの電気をつかったクリスマスツリーの点灯イベントを行っているのだそうです。電極を取りつけた水槽に3匹の電気うなぎを入れ、電気うなぎの力を助ける手作りの装置を使って900個もの電球を光らせています。今ではすっかり松島水族館のクリスマスイベントとして定着しています。
|
|
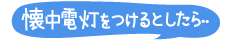 |
実際には『無理』だとしても、理論上ではどうなんでしょう。館長さんに懐中電灯を光らせるとしたら…という計算をしてもらいました。出てきた答えは「水の中を自由に泳ぎまわる電気うなぎから電気をうまく集められれば約3.2秒間つけることができるかも…」。やっぱり省エネ対策には無理があるみたいですね。 |
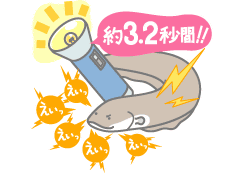 |
※(放電電圧400V、電流2A、放電時間1/1000秒)×5回を前提条件に計算。攻撃用の発電器官からの1回の放電は1000分の1秒くらいの短い電圧を数回連続して出しています。(放電の回数を5回として計算しています。) |
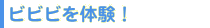 |
電気うなぎの電気を実際に体験できるコーナーがありました。ちょっと小ぶり(といっても体長60cmほど)の電気うなぎの水槽には電気をとりだすための金属の板が2枚。「感電クン」と名付けられた丸いプラスチックの実験装置を手ににぎると、電気うなぎのショックがビビビッと伝わってきます。初めに紹介したようにレーダー役の電気はとっても弱く実験装置を使っても感じることはありませんが、飼育係の方がえさを与えた瞬間…。まちがいなく電気を出していることを体験しました。 |
 |
|

