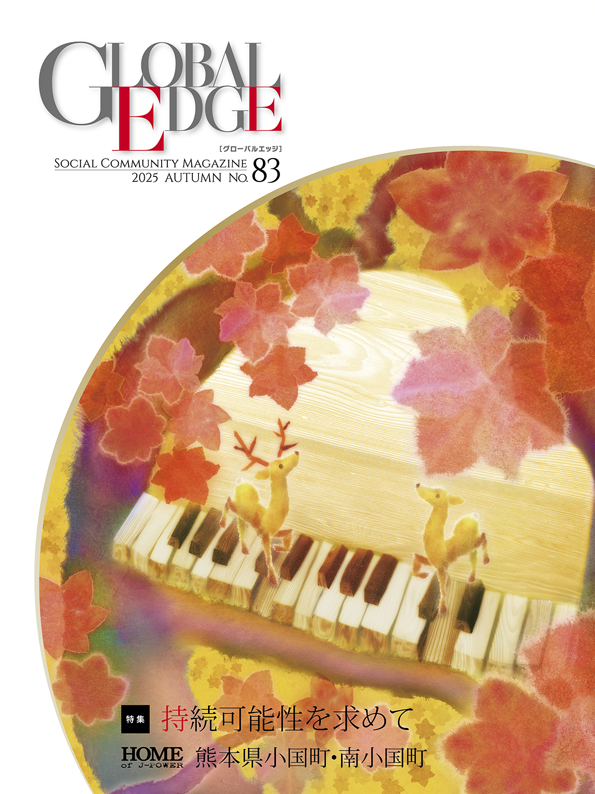廃アルミから水素とエネルギーを
アルハイテック株式会社
匠の新世紀
アルハイテック株式会社
富山県高岡市

我々が日々捨てている食品や錠剤のパッケージにはアルミを使用しているものが多く、家庭ゴミの約1割に含まれるという調査結果も。
そんなアルミ系廃棄物から水素をつくり、再利用する技術を持つ企業を訪ねた。
大量のアルミ系廃棄物 有効活用する道は

企画営業部長 山村賢志さん
1989年に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』という映画をご存じだろうか。その中に、タイムマシン「デロリアン」のエネルギー源として、バナナの皮や空き缶を利用するシーンが登場する。まさにそんな夢を実現するような技術が富山県高岡市にあった。
アルハイテック株式会社は、廃棄されるアルミニウム(以下、アルミ)を資源化し、水素を製造する独自技術で注目を集めている。
同社は2013年の創業だが、この研究開発はそれ以前、2006年頃から始まった。きっかけは、同社先代社長の水木伸明さん(本年5月に逝去)が運送会社の環境事業部に所属していた時、製紙会社から、大量に発生するアルミ系廃棄物(以下、廃アルミ)の処分について相談されたことだったという。
アルハイテック株式会社企画営業部長の山村賢志さんにお話を聞いた。
「アルミは、精錬時に膨大な電力を使う『電気の缶詰』と呼ばれる金属です。一般的に、アルミはリサイクル率が高いといわれているのですが、実はリサイクル率が高いのはアルミ缶だけで、それ以外のアルミ使用のパッケージなどは、生ゴミと一緒に焼却されたり、そのまま埋め立てられることがほとんどです。そのような形でアルミが捨てられていく状況に、水木は強い問題意識を抱いたようです」
ジュースや清涼飲料の紙パック、ヨーグルトのふた、錠剤のパッケージなどには、アルミ箔が使用されているが、消費者はあまり意識せずに燃えるゴミとして捨てている。驚くことに、家庭から出る燃えるゴミの約1割にアルミが使用されているという報告もある。
相談を受けた水木さんは、富山県内の大学や県立工業技術センター、アルミ関連企業などに廃アルミのリサイクルについて相談して回ったという。
「水木は文系の事務職で、アルミやリサイクル方法についての知識がほとんどありませんでした。素人だったからこそ、遠慮なくいろいろなところに相談できたのではないでしょうか」
富山県は日本有数のアルミ産業の集積地で、精錬や加工など様々なアルミ関連企業があり、アルミの研究者などの専門家がたくさんいたことも水木さんに幸いした。
「専門家に相談してみると、廃アルミから紙やプラスチックを分離し、アルミだけを取り出す技術はすでにあることがわかりました。ただ、そうして取り出したアルミは、薄い膜状のため、熱を加えると燃えてしまい、再溶解できず、リサイクルは難しいと指摘されたそうです。そこで出てきたアイデアがアルミから水素をつくることでした」



様々な団体が協働でアルミのリサイクルを目指した







水木さんのこうした行動が様々な企業や研究機関を巻き込んで、化学反応を起こした。
2009年、北陸地方の企業や研究機関、行政、いわゆる「産官学」が連携し、「北陸グリーンエネルギー研究会」が任意団体として発足(現在は一般社団法人)。北陸地方の10以上の企業・大学・自治体が参加する大きな動きとなり、廃アルミから水素をつくろうという流れができた。2010〜12年には、環境省の補助金を受けて廃アルミから水素をつくり出す本格的な研究がスタートした。
このプロジェクトは概ね次の3段階で進められた。
① 紙を使った廃アルミから紙パルプを分離。
② プラスチックを使った廃アルミからアルミを分離・回収。
③ 分離・回収されたアルミから水素をつくる。
最初に取り組んだのは、廃アルミから紙を分離する「パルパー型分離機」の開発。製紙会社で使われている古紙から繊維を取り出す装置をベースに、水を使って紙を溶解し、紙パルプとアルミ付きプラスチックに分離する機械だ。使用する水を何度も循環させ、低コストで環境にも優しい機械をつくりあげた。
続いて取り組んだのが「乾留式アルミ回収装置」。中国の大学の研究を参考に、アルミに付着したプラスチックに600℃前後の熱を加え、自燃(じねん)させることでプラスチックを除去(乾留)し、アルミを分離。プラスチックが自燃するため、外部から熱をほとんど加える必要がなく、低コストで不純物の少ないアルミを回収できる。
そして最後に取り組んだのが分離したアルミから水素をつくる「水素製造装置」だ。
時を同じくしてアルハイテック株式会社が設立され、プロジェクトは同社が引き継いで進められることになった。
何度も循環して使え、効率よく水素を取り出す
高校の化学の実験なら、アルミを水酸化ナトリウムと反応させ、水素を発生させることができるが、それは1回だけの反応で、繰り返し行うことはできない。同じ反応液を使用し、何度も水素をつくり続ける技術はないのか。探してみると、スペインの大学がその技術を持っていることがわかった。同大学からベースとなる技術を導入、それに独自技術を追加し、「水素製造装置」を完成させた。
この装置では水素を連続して発生させるだけでなく、水酸化アルミニウムを取り出すこともできる。水酸化アルミニウムは、幅広い用途を持つ工業原料で、目標とした廃アルミのリサイクルも実現可能となった。
2016年には県内の印刷会社にこの3つの装置を設置し、実証実験を行い、廃アルミから水素がつくれることを確認した。
現状、商業化の鍵は水素需要の高まりと安定的な原料供給だ。一般家庭からの廃アルミ回収は効率が悪いため、当面は製薬会社など廃アルミを大量排出する製造業からまとまった量を調達する方針だ。
コンパクト化によって現地で水素発生と利用を

現在同社が取り組んでいるのは、「水素製造装置」のコンパクト化。水素は運搬や保管が難しいといわれる気体だが、乾留アルミの状態であれば半永久的に保存ができ、運搬も容易だ。コンパクトな「水素製造装置」なら、水素が必要な地点に装置自体を移動し、乾留アルミと反応液をセットすれば、すぐに水素を利用することができる。
「開発中の『エ小僧SMART』では、600×600×1,100mmの大きさまで小さくすることができました。この装置では、乾留アルミから水素をつくり、そのまま燃料電池で発電し、充電や通信に使用することができます。被災地で停電になり、通信手段がなくなった時など、緊急的に小規模な電源が必要な場合に有効ではないかと考えています」
「エ小僧SMART」は、反応液が入ったタンクをセットし、投入口から乾留アルミを投入すれば、水素が発生、燃料電池による発電が開始される。反応液のタンク1つで3日間は稼働し、スマートフォンなどの充電に利用できる。
実はこの「エ小僧SMART」、純度の高い乾留アルミでなく、紙やプラスチックが付いたままの廃アルミでも、細かく砕いてアルミの接触面を増やせば水素をつくることができるのだという。
アルミの廃棄物でデロリアンが飛行する未来は、すぐそこまで来ているのかもしれない。
取材・文/豊岡 昭彦 写真/斎藤 泉
PROFILE
アルハイテック株式会社
2013年の創業の廃アルミを活用した水素・資源循環技術開発企業。廃アルミニウムを活用し、水素を効率的につくり出し、クリーンエネルギーを生み出す革新的な技術の開発とその社会実装に取り組んでいる。