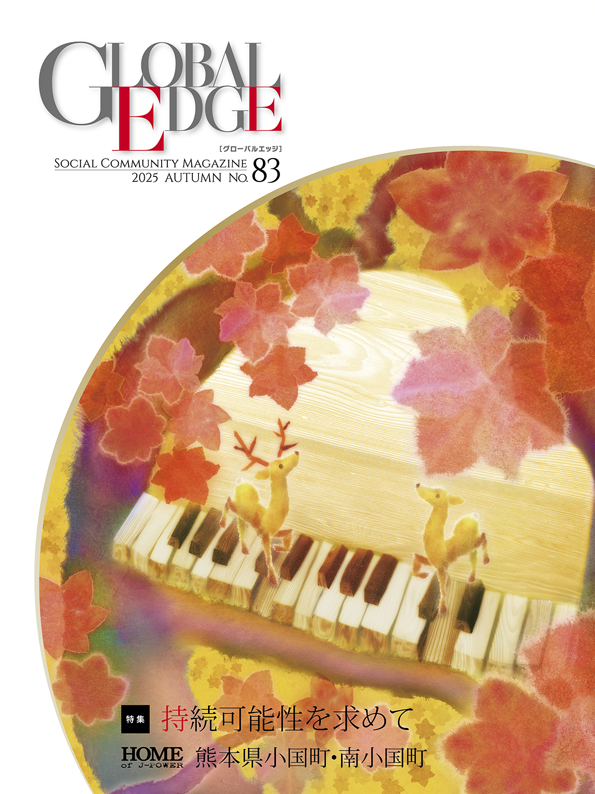世界認識を再構築するために歴史の鏡を磨け
寺島 実郎
Global Headline
2025年8月15日を迎え、日本は戦後80年を総括すべき時を迎えている。「なぜ、戦争になったのか」については特にしっかりと踏み固めなければならないし、その歴史認識を踏まえて、世界史の中での戦後日本を検証しなければならない。
こうした時に大切なのが、私が常々言及してきた「全体知」だ。「知」には「専門知」、「総合知」、「全体知」の3つがあるが、専門知や総合知だけでは課題解決力は高まらない。優先順位を見極め、本質を構造的に変えるには、全体を俯瞰するとともに、どのような歴史的文脈の中に立っているのかを理解すること、すなわち「歴史の鏡を磨くこと」が欠かせない。
近代史に関する日本人の認識の薄さは大きな問題だ。かつて高校教育では日本史と世界史が分断され、近代史の教育は手薄になりがちだった。その結果、明治維新から日中戦争、太平洋戦争へと日本が突き進んだ経緯について正しく理解できていない日本人が多くいるのではないだろうか。
私は本年9月に岩波書店から書籍『世界認識の再構築 一七世紀オランダからの全体知』を上梓した。本書は、岩波書店の雑誌「世界」で15年にわたって探求してきた連載をまとめたもので、近代の原点を17世紀オランダに求め、以降の歴史を丹念にたどっている。
なぜ、オランダなのか。17世紀のオランダは宗教改革後の共和国として民主主義の萌芽を持ち、通商国家として世界貿易で栄えた。例えば、米国の原点ともいわれるピルグリム・ファーザーズは英国からアメリカ大陸に渡ったと思われているが、実際はオランダに12年間亡命した後、新大陸に渡っていったし、ロシアのピョートル大帝は、青年期にオランダの造船所で働き、その体験が首都建設やアジアへの接近の原点になっている。
また、オランダが江戸期の日本と唯一交流した西洋の国だったことも重要だ。海外との交流を断っていたとされる江戸幕府は、オランダを「世界への窓」として世界情勢を意外なほど入手できており、欧米列強がアジア諸国を次々と植民地化したこともわかっていた。
明治維新は、尊皇攘夷(そんのうじょうい)を倒幕のエネルギーとして実現したが、欧米列強に触れた明治政府は近代化へと軌道修正し、富国強兵に邁進(まいしん)して、「遅れてきた帝国主義国家」として、アジアに植民地を求めていくことになる。こうした歴史の本質は、現代の国際関係を読み解く鍵になるとともに、それによって地政学の本質が見えてくるだろう。本書は、そのための羅針盤となることを目指している。
歴史が現在から過去への問いかけであるならば、未来への指針もこうした思考の積み重ねから見えてくるはずだ。
(2025年8月6日取材)
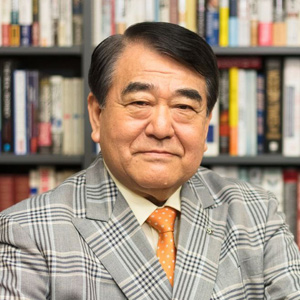
PROFILE
寺島 実郎
てらしま・じつろう
一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長。1947年、北海道生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、三井物産株式会社入社。調査部、業務部を経て、ブルッキングス研究所(在ワシントンDC)に出向。その後、米国三井物産ワシントン事務所所長、三井物産戦略研究所所長、三井物産常務執行役員を歴任。主な著書に『世界認識の再構築 一七世紀オランダからの全体知』(2025年、岩波書店)、『21世紀未来圏 日本再生の構想──全体知と時代認識』(2024年、岩波書店)、『ダビデの星を見つめて 体験的ユダヤ・ネットワーク論』(2022年、NHK出版)など多数。メディア出演も多数。
TOKYO MXテレビ(地上波9ch)で毎月第3日曜日11:00〜11:55に『寺島実郎の世界を知る力』を放送中です(見逃し配信をご覧になりたい場合は、こちらにアクセスしてください)。