出会いと協働が織りなすカーボンニュートラル社会の実現
渡部 肇史 × 伊藤 仁
Global Vision
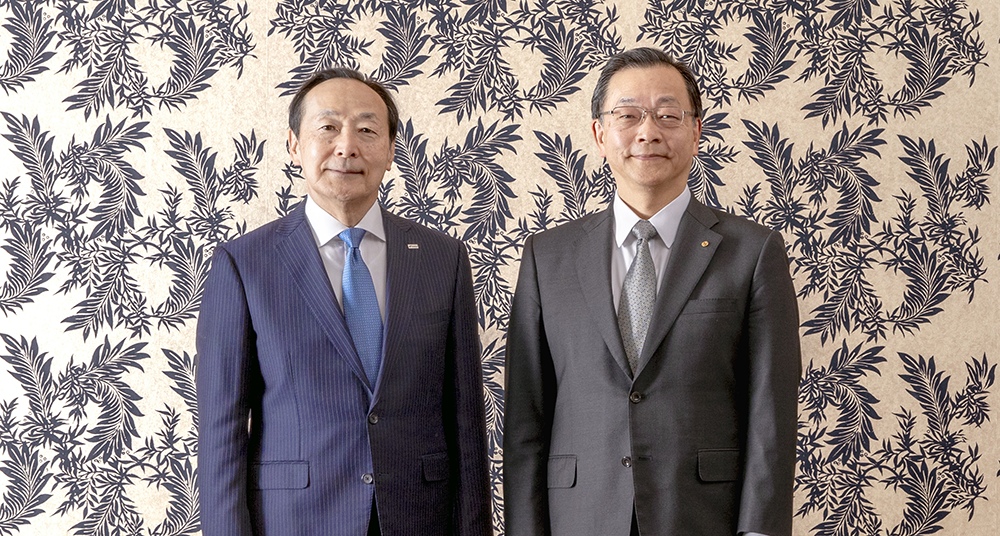
J-POWER会長
渡部 肇史
日本商工会議所・東京商工会議所専務理事
伊藤 仁
国内事業者の99.7%を占める圧倒的多数の中小企業。
省エネ・脱炭素・GXの力で日本のカーボンニュートラルを実現するにはその小さくて大きなパワーの集結が不可欠だ。出会いの場をどうつなぐか。
中小企業が多く集う日商・東商の伊藤仁専務理事と語り合う。
全国の中小企業を結ぶ地域総合経済団体
渡部 J-POWERはつくった電気を主に地域の電力会社などに販売することで、電力を供給している会社です。そのため、実際に電気を使っていただく需要家の皆様との直接的な接点は、実はそう多くはありません。本日はそうした企業が数多く加入される日本商工会議所(以下、日商)、東京商工会議所(以下、東商)の専務理事を務めておられる伊藤さんを通じてぜひ、私ども電力供給者へのご要望をお聞きできたらと楽しみにしておりました。
伊藤 確かに電力の需要家、そして供給事業者も含めてたくさんの企業に参加していただいています。東京23区内の事業者で構成される東商の会員が約8万5,000件。同様に地域の事業者を会員とする商工会議所が全国に515ありまして、それらを合計すると約126万の会員数となります。日商というのは、こうした地域の商工会議所をつなぐ連合組織です。
渡部 もとは東商が最初に誕生して、そこから全国各地へ広がっていったと伺っています。
伊藤 1878年(明治11年)年に渋沢栄一によって設立されたのが始まりで、当時は「東京商法会議所」と呼んでいました。同時期に大阪、神戸でも発足し、全国の主要都市へと波及していきます。地域経済の活性化を使命とする、いわば地域総合経済団体としての民間組織です。そこからさらに日本経済の全体像を見据えるために連携しようという趣旨で、1922年(大正11年)に日商が設立されました。
渡部 もう150年近い歴史があるのですか。私も資源・エネルギー部会長を拝命しておりまして、その活動で最近、会員の方々とお会いする機会が増えてきました。実に多彩な業種、業態の企業がいらっしゃるのですね。広がりの大きさを感じます。
伊藤 ご協力ありがとうございます。日商・東商の会員はほとんどが中小企業です。何を基準に中小企業とするかは諸々あるのですが、中小企業庁の統計によると事業者数は全国で約336万社を超えるそうです(2021年)。126万の商工会議所会員が、その約3分の1を占める計算です。しかも日本企業全体の99.7%は中小企業ですから、まさに日本経済の縮図がここにあるといっていいかもしれません。
渡部 中小企業が元気になれば、日本経済も元気になる。そのための支援をされているわけですね。
伊藤 会員は中小企業だけに限定していませんが、中心となる活動は中小企業が抱える経営課題への解決サポートです。これは会員であるなしを問いません。また、企業の活力が高まるよう行政や政治に対して働きかける政策提言活動にも、日商を中心に力を入れています。同時に、各地の自治体や事業者と連携した、観光やビジネスを通じた地域振興活動も私たちの重要な役割です。

省エネからGXへ 行動変容を促すカギ
渡部 企業にとって、地球温暖化対策、カーボンニュートラル社会の実現、そのための省エネ・脱炭素化は、もはや組織の大小を問わない経営課題といえそうです。中小企業を支援されるお立場から見て、会員の方々の受け止め方はいかがですか。
伊藤 経済産業省が発表した「クリーンエネルギー戦略 中間整理」(2022年5月)を見ますと、日本全体の温室効果ガス排出量のうち中小企業からの排出が1〜2割を占めています。それなりに大きな割合ではありますが、中小企業の総数からすれば1社あたりの値は小さいわけで、削減効果を上げていくには省エネ・脱炭素の取り組みの全体的な底上げが重要になると思います。
一方、日商・東商が行った「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」(2024年3〜4月)の結果、約7割の企業が脱炭素に関する何らかの取り組みを実施していることがわかりました。具体的には、省エネ設備の導入や更新、運用改善、またエネルギー使用量・温室効果ガス排出量の「見える化」といったことです。中小企業の課題意識は決して小さくはありません。
ただ、脱炭素に取り組む理由・目的で最も多いのは「光熱費・燃料費の削減」で、約75%でした。中小企業としては、やはり目の前にあるコストの問題が大きい。昨今のエネルギー価格の上昇により、約9割の企業が「経営に影響あり」としていることからもそれは明らかです。
つまり、現状は経済的インセンティブを主な動機として動いている省エネ・脱炭素の取り組みをもう一段進め、クリーンエネルギーへの転換そのものが企業の成長・発展に結びつくような仕組み、すなわちGX(グリーントランスフォーメーション)の取り組みへと昇華させる何かが必要ではないかと見ています。
渡部 そうした行動変容を促すにはどうしたらいいのでしょう。この2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画には、中小企業にとってGXの取り組みは、光熱費・燃料費の低減だけでなく、自社製品のブランド力強化や取引先の拡充にもメリットがあると書かれています。
伊藤 そうですね、2つの方向性があると思います。1つは、B to Bのビジネスにおいて、脱炭素への対応が取引上の付加価値、あるいは競合相手との差別化につながること。これは実際、GXに積極的な大手企業などが自社のサプライチェーンの全体を通じて脱炭素化を求めていく動きとともに加速する傾向にあります。先ほどの実態調査でも、中小企業の4社に1社が、脱炭素に関して取引先から何らかの要請を受けていると回答しています。
もう1つはB to Cです。マーケットとしてはまだ小さいかもしれませんが、多様な消費者・ユーザーの中には脱炭素に関心の高い層が着実に増えつつあります。小回りの利く中小企業だからこそ、そのニッチな市場に切り込み、付加価値を上げていける可能性は高いと思います。
渡部 なるほど。そうした流れをより確かなものにするために、後押しとなる公的支援も必要ですね。
伊藤 例えば、サプライチェーンにおける要請にしても、取引先によって求められる条件が異なるのでは対応しきれません。「この分野の製品に関して基準となるCO2削減量はこの測定法で評価する」というように標準化がなされれば、よりいっそう対応が進むのではないでしょうか。
渡部 サプライチェーン全体の付加価値向上や、大企業と中小企業の共存共栄を目的とした「パートナーシップ構築宣言」というのを政府が推進しています。こうした仕組みを活用する手もありそうです。
伊藤 そう思います。この制度はとかく取引価格の話ばかりが注目されがちですが、グリーン調達を含む企業間の新たな連携を生み出す契機にもなり得るものです。ここに脱炭素のルールを組み込めば、実効性が上がるのではないかと思います。
渡部 発注者の立場からすれば、現実問題、脱炭素への対応が不十分だからといってすぐに取り引きをやめるわけにはいきません。同じサプライチェーンを共有する仲間として、ともに手を携えてGXを促進する方策を考えたいものです。
「知る・測る・減らす」の段階的スキームを展開
渡部 カーボンニュートラル社会の実現に向けて、会員企業の皆様からのご相談はありますか。どのようなことに壁を感じておられるのでしょう。
伊藤 取り組みを進めようにも、それを支える人員や知見や技術が足りないと感じている会員が半数を超えています。加えて、温室効果ガスを減らすには、まず自社から出る排出量を測る必要がありますが、その具体的な算定方法がわからない。さらに、取り組むための資金不足を挙げる企業も少なくありません。
こうした声をまとめると、GXに関する知識や理解を得て、現状を把握し測定したうえで、いざ削減に取り組む、という流れが見えてきます。つまり、「知る・測る・減らす」の3ステップです。そのため日商では今、これら各段階に沿った支援策の強化に努めているところです。
渡部 温室効果ガスの排出量を見える化するツールの導入支援サービスも始めておられますね。
伊藤 日商では従来、排出量算定に使える「CO2チェックシート」を無償で提供しておりますが、中小企業の「測る」をいっそう後押しするために新しいサービスを始めました。それは電気やガスのエネルギー使用量からCO2などの排出量を計測し、クラウドで共有するサービスです。ツール自体は民間事業者が提供するものですが、各地商工会議所はその間をつなぎ、導入支援を行います。
このほか、「知る」ではセミナーやWebを通じた環境・エネルギー関連の情報提供を、「減らす」では資金サポートの一環として、省エネ・脱炭素設備に関する公的助成金への橋渡しなどを進めています。国への政策提言や要望だけでなく、我々自身も実働しようという姿勢です。
地方重視の投資促進策でサステナブルな未来へ
渡部 そうした積極姿勢というのはやはり、第7次エネルギー基本計画にも示された日本を取り巻く最近のエネルギー事情や、将来に向けての政策に即してのことでしょうか。
伊藤 そうですね。気候変動問題だけでなく、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢といった地政学的リスクと絡むエネルギーの安全保障、またデータ利活用の飛躍的進展に伴う電力需要の増加などという複合的な要因によって、日本のエネルギー問題は厳しさを増しています。その中でエネルギー安定供給と脱炭素を両立するために、現実的に我々に何ができるのか。エネルギー基本計画は、その問題意識と具体的方策を示している点で評価できると思います。
渡部 今回のエネルギー基本計画では、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の主力電源化を軸として、原子力を含む脱炭素電源を最大限に活用するとしています。2040年度における電源構成の見通しは、再エネで4〜5割、原子力で2割ですから、合わせて最大7割。つまり、電力供給側の努力でそれが実現すれば、需要家の皆様は購入する電気の7割で脱炭素化を果たすことができる。残り3割にどう取り組むか。それは企業の省エネ努力などに負う部分も大きくなります。そういった認識は会員の皆様とも共有可能ですか。
伊藤 実際のところ、どこまで理解が進んでいるかはわかりませんが、カーボンニュートラル社会に向けてエネルギー源の電化シフトがいっそう進むことが明白である以上、省エネは避けて通れない課題です。中小企業はまずそこから、問題意識の共有を図らなければなりません。
いずれにしても、エネルギー源の非化石化を進めるには再エネが不可欠ですし、原子力も欠かせない。そこには当然、大きな投資が求められます。そこで私たちが声を大にして申し上げたいのは、ぜひ地方を重視した投資促進策を打ち出してほしいということです。実際、再エネなどの新たな電源の開発に適した場所は都市部には少ないと思います。
渡部 おっしゃるとおりです。供給側の立場としても、投資回収の予見性を高め、電力投資をサステナブルにするための事業環境整備に向けた支援策はぜひとも必要です。金利が上がり、インフレが進む傾向にある今の状況ではなおさらです。
発電事業に関連する産業の裾野は広く、電力投資によって様々な波及効果が期待できます。地域経済の活性化にもそれを生かし、エネルギーの供給面と価格面の双方で安定化に貢献したいものです。
伊藤 例えば洋上風力などは、そうした地域の産業振興やサプライチェーンの構築に大きく貢献してくれそうです。資材費高騰などの壁はあるものの、開発段階はもとより、その後のメンテナンスなどの需要も合わせると大きな経済効果が期待できるのではないでしょうか。
渡部 まさにそうした観点も踏まえて当社も今、洋上風力の開発に力を注いでいるところです。北九州市沖の響灘(ひびきなだ)で今年度中の運転開始を目指して建設中のウインドファームもその一つで、日本最大規模の洋上風力発電所となります。ここには東京都庁の高さ243mにも匹敵する25基の巨大な風車が建ち並ぶのですが、その点検保守に見込まれる業務も幅広く、コンスタントに経済効果を生むものと考えています。


多様なアクターをつなぐ出会いと協働の場を
渡部 供給側と需要側で立場は異なりますが、ともに力を合わせることはできそうですね。連携の可能性についてどんな感触をお持ちですか。
伊藤 先ほど人材やノウハウの不足に悩む会員が多いと申し上げましたが、そうした際の相談先として、設備機器メーカーや電力・ガス会社を挙げる声がともに2割を超えています。自社にない知見を持つ企業との協力に可能性を見ているわけです。
その声に応えて東商は、「つどう」、「つながる」、「つくる」をテーマとした「Tosho攻めの脱炭素」事業を始めました。①中小企業同士が集い、専門家の指導を受けて実践的に学ぶ東商脱炭素“塾”、②取り組みを進めたい中小企業と、それを支援する企業をマッチングする東商脱炭素“市場”、③大学や研究機関との連携で新たなビジネスチャンスをつくる東商脱炭素“ラボ”の3つのプログラムがあります。すでにこれらに参加して先駆者のノウハウを知り、成果を上げる会員企業も現れました。
渡部 商工会議所を一つの結節点として、業種や業態、規模の違いを超えた縦横無尽の出会いを生む。素晴らしい取り組みですね。エネルギーの分野でも広がりがありそうです。
伊藤 洋上風力の例にもあるように、自然の恵みを生かす再エネは、ローカルな立地においてこそ存在価値を発揮するものでしょう。そこに地域の総合経済団体としての商工会議所が介在してハブとなり、新たな協働関係を誘発することは十分可能ではないでしょうか。
渡部 まさに持続可能な社会をつくるキーワードは「つなぐ」ですね。
伊藤 私が日商・東商での務めを通じて、改めて強く感じたのはそのことです。「失われた30年」からの脱却に必要とされるのは、異なる分子の結合から触発される変革ではないか。そこには地域や業種を超えた横のつながりがあり、世代をまたぐ縦のつながりがある。日本全国を舞台にその場をつくり、変革への触媒となることこそ、商工会議所の本質的な役割ではないかと考えています。
渡部 私どももぜひ、その連携の輪に加えてください。最後に、電力事業者に向けて叱咤激励の言葉を。
伊藤 「野心を持ったリアリスト」であってほしいと思っています。技術や経済、市場の現実を見据える冷静な目と、あるべき理想の実現に向けて野心を燃やす熱い眼差し、その両方をどうか忘れないでください。
渡部 ありがとうございました。
(2025年2月26日実施)
構成・文/松岡 一郎(エスクリプト) 写真/大橋 愛
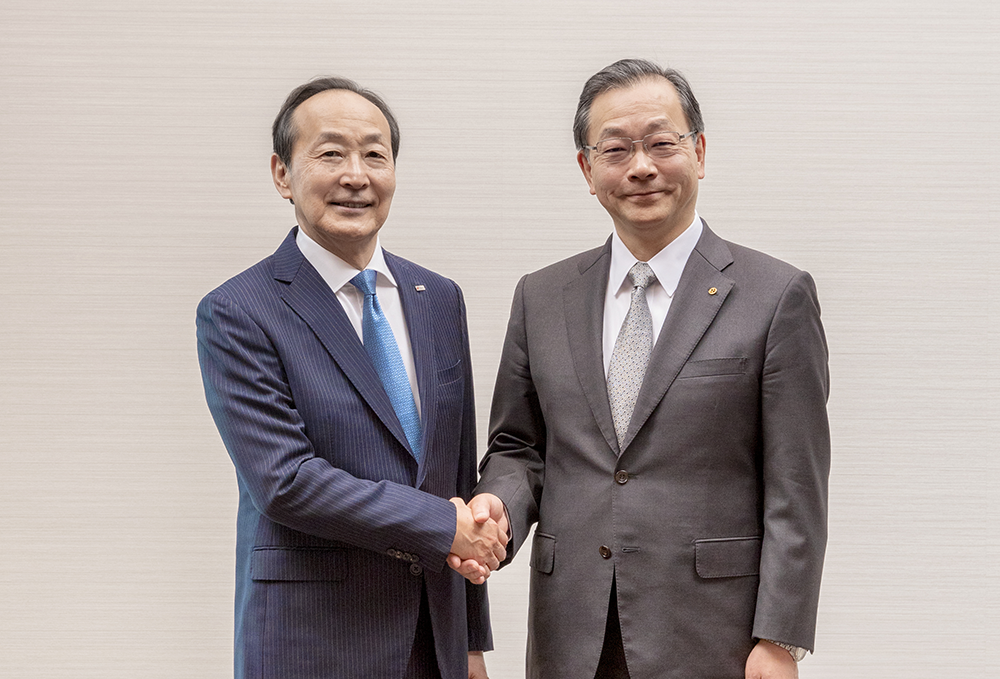

PROFILE
伊藤 仁(いとう・ひとし)
日本商工会議所・東京商工会議所専務理事。1959年生まれ。1982年、東京大学経済学部卒業。同年に通商産業省(現経済産業省)入省。2011年、内閣官房内閣審議官(副長官補室)、2013年、復興庁統括官、2014年以降特許庁長官等を歴任し、2024年7月より現職。


