トランプ2.0の新局面 これからの米中関係をどう考えるか
寺島 実郎
Global Headline
米国でトランプ大統領の第2次政権が1月に発足して以降「米中対立が極まる」と思われてきたが、いざ蓋を開けてみると、この政権は意外なほど中国に配慮していることが次第にあぶり出されてきた。
例えば、1月24日に米中外相による電話会談が行われたが、米国のルビオ国務長官は「米国ファーストの対中関係」を強調した。そして、「台湾独立を支持せず」と明言し、中国が最も触れられたくない人権や民主化弾圧、少数民族抑圧にも一切触れなかった。これはトランプ政権が実利に基づいてディール(取り引き)すると宣言し、米中双方に利益のあることを実行するというスタンスを示したということだ。さらに、トランプ氏はこれまで中国への追加関税は60%と言ってきたが、実際には10%(その後20%に引き上げ)とするなど、トーンダウンしている。
トランプ政権がこのような動きに出ている背景には何があるのか。それは中国とロシアの関係に楔を打ち込もうとしていることに気づかねばならない。
ウクライナ侵攻後、ロシアの中国への依存は顕著で、2024年のロシアの中国に対する原油輸出は侵攻前の約4倍になっている。石油や天然ガスなどのエネルギー輸出がロシアの外貨獲得の主な手段で、経済制裁によって欧州への輸出が難しくなっている状況では中国だけが頼りというような状況だ。一方の中国としても、ロシアの依存によるメリットを感じながらも、侵略戦争を起こしているロシアを支援していると見られることは国際的に都合のいいことではない。
さらに、東南アジア諸国がBRICSに加盟、あるいは加盟申請をして拡大しようとする中、中ロが主導しBRICSが反米同盟のようになることを回避する意味合いもあるだろう。
要するに、激しく対立すると思われていた米中関係は、実際は「選別的対立」であり、半導体やAIなどの先端技術分野では対立するものの、それ以外の分野では協力体制を築いていこうとしている。その背景には、米中がファンダメンタルな面で相互依存関係にあり、2024年の米中貿易は前年よりも増加し、5,825億ドル(日米貿易の約2.6倍)に上っているという状況がある。
米中が対立すれば米国が日本に近寄ってくれると思うのか、日本にはこれを望むような雰囲気もある。だが、「中ロ蜜月・米中対立」といった一面的な見方では世界情勢を見誤る。米中関係に大きなパラダイム転換が起きようとしている。
これに対し日本はどのように向き合っていくのか。冷静に状況を見極め、どのような環境にも対応できるよう重心を低くして構えることが必要だ。
(2025年2月27日取材)
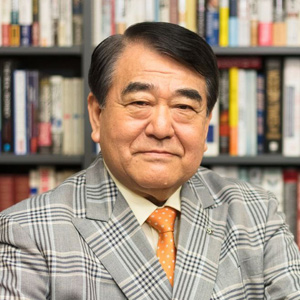
PROFILE
寺島 実郎
てらしま・じつろう
一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長。1947年、北海道生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、三井物産株式会社入社。調査部、業務部を経て、ブルッキングス研究所(在ワシントンDC)に出向。その後、米国三井物産ワシントン事務所所長、三井物産戦略研究所所長、三井物産常務執行役員を歴任。主な著書に『21世紀未来圏 日本再生の構想──全体知と時代認識』(2024年、岩波書店)、『ダビデの星を見つめて 体験的ユダヤ・ネットワーク論』(2022年、NHK出版)、『人間と宗教あるいは日本人の心の基軸』(2021年、岩波書店)など多数。メディア出演も多数。
TOKYO MXテレビ(地上波9ch)で毎月第3日曜日11:00〜11:55に『寺島実郎の世界を知る力』を放送中です(見逃し配信をご覧になりたい場合は、こちらにアクセスしてください)。


