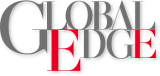「空飛ぶクルマ」を現実に
福澤 知浩
Opinion File

2023年商品化を目標に研究開発進行中
空飛ぶクルマがビルの隙間を駆け抜ける。まるでSF映画のような光景が、2050年には現実となるかもしれない。18年には政府が「空の移動革命」に向けたロードマップ(※1)を定め、新たなモビリティの開発に本腰を入れ始めた。国内でも大手企業やベンチャーが入り乱れ競争が激化している。そんな中で、先頭を走るのが株式会社SkyDrive(以下、スカイドライブ社)だ。
「東京オリンピックの開催期間に合わせて、デモフライトを実施する予定です。しかし、これはあくまでも通過点。23年には空飛ぶクルマの第一弾を商品化したいですね」
夢のような話をさらりと語るのは福澤知浩代表取締役だ。具体的には、時速100㎞で20?30㎞の距離を飛行できる二人乗りの機体を年間数台のペースで販売していきたいという。想定価格は3000万~4000万円程度。超高級車を新車で購入するような富裕層にとっては、十分に魅力的な選択肢となるはずだ。
とはいえ、商品化に向けての課題は少なくない。中でも最も高いハードルとなっているのが安全性の向上だ。モーターやバッテリー、プロペラなど、各パーツが故障する確率を合計して求められる事故率を、航空機と同じ水準まで引き下げなくてはならない。
「空飛ぶクルマには、ドローンの1000~1万倍の安全性が求められます。万が一、墜落した時に及ぼす被害がドローンの比ではないからです。飛行中にモーターの一つが止まっても、バッテリーに不具合が起きても安全に着陸できなければならない。あらゆる事態を想定して、実証実験を重ねています」
自動車のように日常に溶け込むモビリティを目指すからには、騒音対策も欠かせない。ジェットエンジンで飛行する航空機ほど騒がしくはないものの、プロペラの風切り音は無視できるレベルではないのが現状だ。
「そこはプロペラの形状を工夫することで対応できると考えています。プロペラをカバーで覆ってしまうという手もあるし、技術の進化によってはノイズキャンセリング機能も搭載できるかもしれない。23年までには、飛行中の風切り音を、航空機の離発着時に客室内で感じる音よりも小さくしたいですね」
技術面以外にも課題はある。認証制度の問題だ。そもそもまったく新しいモビリティである空飛ぶクルマには、機体やライセンス、離発着場、飛行ルートなどの認証を司る機関が存在しない。そのため、認証の枠組みを決めるところから議論を始めなければならない。
「機体に関しては、航空機と同じようにグローバルな認証制度が必要になるはずです。ライセンスや離発着場については国と交渉していくしかない。航空ルートは、まずは川や海などに限定し、そこから徐々に飛行可能なエリアを拡大していくという流れになるはず。まだまだ詰めるべきことは山積みですね」

(c)CARTIVATOR/SkyDrive
イノベーティブなモビリティをつくりたい
空飛ぶクルマの実用化に向けて奔走する福澤さんだが、2年前まではトヨタ自動車に勤める、会社員だった。一体何が彼を、空飛ぶクルマの開発へと駆り立てたのだろう。
「のちに有志団体の共同代表となる中村翼さんと、飲み会で偶然出会ったことがきっかけです。イノベーティブなモビリティをつくろう! とその場で意気投合してしまって(笑)。それから二人で様々なアイデアを出し合い、最終的に残ったのが空飛ぶクルマでした」
12年には自動車業界で働く若手技術者を中心に十数人の仲間を集め、新たなモビリティの開発を目指す有志団体CARTIVATOR(カーティベーター)を結成した。ここでも議論を繰り返し、「自分たちが開発すべき新しいモビリティとは空飛ぶクルマである」と意見が一致し、本格的な開発がスタート。とはいえ、当時はほとんどのメンバーがフルタイムの会社員だったため、作業にあてられるのは平日夜と土日に限られていた。それでも開発開始から1年を待たずに1/5スケールの試作機の試走、飛行を成功させられたのは、メンバーの熱意がなせる業だろう。さらに15年にはクラウドファンディングを通じて260万円を調達。これをきっかけに認知度が急上昇し、団体の規模も一気に拡大した。
「機体のスケールを大きくしていくタイミングで、航空系の技術者を始めとした、様々なバックグラウンドを持つメンバーが増えたことはありがたかったですね。一般的に機体のサイズが倍になると、機体の制御や管制の難易度は4倍に跳ね上がります。各分野のノウハウを結集できなければ、ここでプロジェクトが頓挫していたかもしれません」
もう一つ追い風となったのがドローン市場の急成長だ。空飛ぶクルマにも応用できるモーターやバッテリー、電子チップなどの品質が向上し、高性能かつ軽量な部品を安価に揃えられるようになった。各分野の専門家がこれら最先端技術を即座にキャッチアップしながら開発を進めることで、16年にはついに1/1スケールでの飛行実験に成功した。
「プロジェクトが一気に現実味を帯びた瞬間です。単に夢を語るのではなく、事業としてきちんと成立させたいと思ったのもこの時です。そのために資金調達をもっとスムーズにできるようにしたかった。そこで18年にスカイドライブ社を立ち上げるに至りました」
19年5月には愛知県豊田市と協定(※2)を結び、豊田市内に日本最大級の飛行試験場とラボを設けた。さらに19年9月には、第三者割当増資および助成金で15億円を新たに調達。福澤さんの狙い通り、会社の立ち上げによって空飛ぶクルマの開発はさらに加速した。
空飛ぶクルマは私たちの暮らしを変える
スカイドライブ社の描くビジョンは、23年のさらにその先へと続いている。まずは26年までに空飛ぶクルマの量産体制を整える予定だ。価格も順次引き下げていき、40年までに1000万円台を目指すという。
「30年頃には操縦も自動化されると予想しています。そうなればライセンス取得のハードルが大きく下がるはず。さらに50年までには自動操縦機能を備えた空飛ぶクルマが、200万~300万円で購入できるようになっているでしょう。文字通り、誰もが自由に空を飛べる時代の到来です」
空飛ぶクルマが広く普及することで、私たちの暮らしはどう変わるのだろう。真っ先に期待できるのが渋滞の解消だ。地上とは異なり、空中では空間を立体的に利用できる。高度を変えることで折り重なるように移動できるのだ。そのため空飛ぶクルマが広く普及したとしても、空が埋めつくされる心配はない。
「渋滞や満員電車に巻き込まれるたびに、空はこんなに広いのに、なんで地べたに這いつくばってこんな辛い思いをしなきゃならないのだろう、と感じます(笑)。現在は多くの人にとって、移動は肉体的にも精神的にも苦痛を伴うものになってしまっています。私たちは、それを変えたい。移動をもっと生産的でワクワクするものにしたいのです」
もちろん空には信号もない。目的地まで最短距離で飛べるため、移動時間も大幅に短縮できる。また空飛ぶクルマを前提とした高層建築が増えれば、目的とする階に直接乗り付けられるようになる可能性も高い。そうなれば、エレベーターなどによる移動時間も省略できる。自宅のベランダから、目的地の窓までが一直線につながり、「どこでもドア」のように窓から窓へ移動できるようになるのだ。
「移動時間の短縮によって、都市部への一極集中も解消できます。誰もがもっと自由に住む場所を選べるようになるでしょう。結果的に、人々は離れて暮らすことになると思いますが、その頃にはARやVR技術(※3)も飛躍的に発展しているから、実際に顔を合わせなくてもコミュニケーションに問題はないはずです。一方で本当に会いたい人には、どんなに離れていても空飛ぶクルマで会いにいける。そんな二極化の時代が訪れると予想しています」


(c)CARTIVATOR/SkyDrive
日本のものづくりの後継者として
同社の描くビジョンは明確で、私たちをワクワクさせてくれる。しかし、どこか夢物語のように感じられてしまうのも確かだ。そんな疑問を率直にぶつけてみたところ、思いもよらぬリアクションが返ってきた。
「私たちの描く未来は、多少の時間のズレはあったとしても必ず実現します。クルマは空を飛び、運転は自動化される。技術的にそれは間違いありません。だから問題は、“実現できるか”ではなく“誰が実現するか”です」
福澤さんが意識するのは、海外勢だ。空飛ぶクルマで世界初の有人飛行を成功させた米国の開発チームには、一日の長がある。有人飛行の回数では、中国の開発チームが頭ひとつ抜けている。ほかにもグーグルの共同創業者であるラリー・ペイジ氏が支援する「Opener」、配車サービスで知られるウーバー・テクノロジーズの「Uber Air」など新興勢力の躍進も目覚ましい。日本ではトップを走るスカイドライブ社だが、世界全体でみると一位集団とはわずかだが差があるようだ。ここから巻き返し、空飛ぶクルマ市場で生き残るために、どんな戦略があるのだろう。
「何よりの武器は安全性の高さ。これは日本のものづくりのお家芸です。今でも日本車は外国車に比べて初期不具合の件数が少ない。その品質の高さを空飛ぶクルマにも生かしたいと考えています。もう一つの武器はコンパクトさです。欧米では有翼式の空飛ぶクルマも開発されていますが、私たちはコンパクトなプロペラ式にこだわりたい。これは日本の一般的な住宅からの離発着を想定したものですが、こうした設計思想は同じく人口密集度が高いアジア各国でも受け入れられるはずです」
安全性とコンパクトさ。かつて世界を席巻した日本のものづくりの2つの特徴を受け継ぐこと。これこそがスカイドライブ社が世界と戦うための基本戦略だ。取材の最後に「それともう一つ、忘れてはいけない大切なポイントがあります」と福澤さんは付け加えた。
「それはカッコ良さです。どんなに安心で快適でも、見た目が悪かったら台無し。やっぱりクルマはカッコ良くないとダメなんです」
世界中の誰もが日本製の「カッコ良いクルマ」に乗って空を飛び回る。そんな未来を、スカイドライブ社がつくってくれるはずだ。
スカイドライブ社の沿革
2012年 CARTIVATOR活動開始
2014年 「空飛ぶクルマ」の開発に着手
2015年 クラウドファンディングで資金調達
2016年 フルサイズの無人機飛行試験
2018年 スカイドライブ社設立
2019年 有人飛行試験
2020年 デモフライト
2023年 有人機販売開始
2026年 有人機量産開始
2030年 無人運転の実現
2040年 有人機が1000万円台に
2050年 誰もが自由に空を飛べる時代に
取材・文/立古 和智、福地 敦 写真/竹見 脩吾
KEYWORD
- ※1ロードマップ
経済産業省と国土交通省が合同で開催した「空の移動革命に向けた官民協議会」をまとめたもの。2023年までに物の輸送、2030年代には地方においての人の移動の実用化を目指すことが示された。 - ※2豊田市と協定
2019年5月、豊田市とCARTIVATOR、株式会社SkyDriveの3者は『新産業創出へ向けた「空飛ぶクルマ」開発に関する連携協定』を締結した。 - ※3ARやVR技術
ともにAugmented RealityとVirtual Realityの略で、ARは拡張現実、VRは仮想現実と訳される。ARは、現実の映像の上に、CGなどを重ねて表示するのに対し、VRはすべてCGで制作し、現実のように感じさせるもの。

PROFILE
福澤 知浩
株式会社SkyDrive代表取締役
CARTIVATOR共同代表
ふくざわ・ともひろ
東京大学工学部卒業後、2010年4月にトヨタ自動車に入社。自動車部品のグローバル調達に従事。同時に多くの現場でトヨタ生産方式を用いたカイゼンをし、原価改善賞受賞。2017年1月に福澤商店株式会社を設立。数十社にて経営コンサルティング、現場改善コンサルティングプロジェクトを実施。内2社は役員として経営参画。トヨタ在籍時代に有志で始めた『空飛ぶクルマ』の開発活動『CARTIVATOR(カーティベーター)』の共同代表を務める。開発加速と事業化を見据え、2018年7月に株式会社SkyDriveを設立し、代表取締役に就任。